
麻木久仁子さん
×
田城孝雄教授
「がんとともに
生きるということ」
スペシャル対談
2012年に初期の乳がんが見つかり
手術を受けた“がんサバイバー”である、
タレントの麻木久仁子さん。
2023年4月に放送大学に入学して
『がんとともに生きる』など4科目を受講、
がんにまつわるさまざまな知識を
深めました。
今回は『がんを知る』
『がんとともに生きる』の
主任講師である田城孝雄教授と改めて対面、
「がんとともに生きるということ」を
テーマに対談を行いました。
(対談実施:2023年6月)

田城教授(左)・麻木氏(右)
-
がんは怖がらなくていい病気
-
麻木:いつもはパソコンの画面上でお目にかかっている先生と直接お話ができて、光栄です。
-
田城:こちらこそ、受講生の方と直接お会いでき、非常に緊張しております(笑)。様々なメディアでもお話を拝見しておりますが、麻木さんもがんのご経験がおありだそうですね。
-
麻木:はい、私は50歳を目の前にして、右胸と左胸両方にがんが見つかりました。タイミングよくがん検診を受けて、非常に早期に発見できたことは幸運でした。すぐに手術をし、放射線治療とホルモン治療を並行して行い、10年が経ちまして少しホッとしているところです。
-
田城:ご自身の体験談をもとに、各地でがんに関する活動をされていらっしゃるのですね。
-
麻木:人前でがんの経験談をお話ししたりする機会が増えていくと、がんサバイバーの方と多くお会いし、「がんはこんなに身近なものなのか」と気づかされます。そこで「がんをもっと体系的に学びたい」「社会ががんと向き合うためにどういうシステムを設けているのかを知りたい」と思い、田城先生が主任講師を務める授業『がんとともに生きる』を履修しました。
-
田城:「日本人の2人に1人ががんになる」と言われていますが、これは人生のどこかでがんになるというニュアンスを含んでいます。実は私の妻も乳がんで、最初に右、7年後に左に見つかりました。私は消化器内科医のため、父が胃がんになったときは自分の専門分野と言うこともありそれほど慌てなかったのですが、妻が乳がんになったときはおろおろしましたよ。
-
麻木:専門外のところですと、先生といえどもおろおろされるのですね!
-
田城:当時は、実際の状況になってわかることもありました。
-
麻木:私も以前から「がんは身近なものだよ」とさんざん聞いていたものの、自分がなるまでは他人事だったので、実際に自分が乳がんになったとき、あまりにもがんについて知らないことが多かったと愕然としました。
-

-
田城:妻の乳がんを知った友人・知人から「実は私も乳がんで……」という話を聞くこともしばしばで、がんの中でもとくに乳がんはありふれた病気になっていると感じます。男性も乳がんになりますが、とくに女性の乳がんは非常に多く、9人に1人は乳がん、という状況です。
-
麻木:10年前は12人に1人という数字でしたが、そこからさらに割合が高くなったのですね。
-
田城:男女半々の40人クラスだとすると2~3人は乳がん、ということになりますね。ただ乳がんは治療がよく効きますので、がんにかかった後も10~20年、元気でいらっしゃる方も多いです。
-
麻木:自分のがんをきっかけに、友人や知人、仕事仲間からがんであることを打ち明けられたり、周囲にがんで亡くなる方が出てきたりと、がんにまつわる話が耳に入ってくることが増え、がんは身近なものだと肌で感じます。
-
田城:かつてはがんであることを隠す時代があり、また「がんになったら助からない」と言われていた時代もありました。しかし今は麻木さんのようにがんであることを公にする人も珍しくありません。オープンに話すことで、がんの仲間の輪ができるといういい側面もあります。また、早期発見・早期治療をすると、多くの種類のがんは完治もしくは10年、20年の生存も期待できるのが普通になってきていますね。
-
麻木:私の場合は早期発見でしたし予後もよかったので、比較的落ち着いてがんのさまざまな情報に触れることができました。
-
田城:もちろん中には非常に進行の早いがんもあり、残念ながら亡くなる方もいらっしゃいます。しかし、がんになった事実に苦しんでおられる方や、誤った情報で不安や心配が増幅している方に「正しい情報を正しく知れば、がんは決して怖いものではない」と伝えたいですね。
-
麻木:私も当初、主治医の先生からそのような説明をされて本当に心が楽になりました。でも、より深刻な病状で初めてがんの情報を探すことになるととても大変だと思いますから、元気なうちに最低限、正しい情報を集める準備をするというのが大事ですね。私自身ができていなかったからこそ、反省を込めてそう思います。
-
「正しい情報」を取捨選択するための学び
-
田城:授業を受けてみて、どんな学びがありましたか。
-
麻木:まず感じたのは、情報の重要性です。現代はあまりにも情報が溢れすぎていて、重要な情報から怪しい情報まで玉石混交、しかもどちらの情報へのアクセスも非常に容易です。大型書店でも、がんのスペースにはたくさんの本が並んでいます。今回、授業を受けてから改めてそのコーナーを見てみると、いかに本のラインナップが玉石混交かに驚きました。しかも“石”のほうが多かったりするんです。
-
田城:雑誌やテレビなどメディアでもがんがテーマに取り上げられる機会は多く、皆さんの関心の高さを感じます。その中で注目を集めるためには、エキセントリックなワードを入れなければならず、少しずつ正しい情報からは乖離していきます。
-
麻木:売れている本だからといって、本当に正しい情報を載せているかどうかは分かりませんし、実は隅っこにひっそりと置いてある本こそ、正しい情報だったりしますよね。
-
 田城:エキセントリックな内容のほうが売れてしまうという流れは、がん診療に携わる我々からすると懸念のひとつです。ネットで個人が気安く情報を上げられますから、どれが正しい情報なのかが判断しづらいことがあります。麻木:授業での学びを通じ、正しい情報を選び取る重要性を改めて感じました。そんな中、先生の授業で、今はがん対策基本法の中に「小中学校で、がんの教育をする」という項目が入っているということを知り、非常に大きな希望を感じました。田城:小学校や中学校で教えるとなると文部科学省、教育委員会の管轄ですので、地元の医師会と教育委員会が連携を取り、授業を行うということになります。まだ十分ではないにしろ重要な歩みでしょう。
田城:エキセントリックな内容のほうが売れてしまうという流れは、がん診療に携わる我々からすると懸念のひとつです。ネットで個人が気安く情報を上げられますから、どれが正しい情報なのかが判断しづらいことがあります。麻木:授業での学びを通じ、正しい情報を選び取る重要性を改めて感じました。そんな中、先生の授業で、今はがん対策基本法の中に「小中学校で、がんの教育をする」という項目が入っているということを知り、非常に大きな希望を感じました。田城:小学校や中学校で教えるとなると文部科学省、教育委員会の管轄ですので、地元の医師会と教育委員会が連携を取り、授業を行うということになります。まだ十分ではないにしろ重要な歩みでしょう。 -
麻木:今の子どもたちが大人になったときは、我々世代とは違った心持ちでがんを受け止められるかなと思います。
-
田城:がんに関する基本的な情報をもっていれば、正しい情報に行きつくこともできます。実は『がんを知る』と続編の『がんとともに生きる』を作ることが、私が放送大学に来た理由であり、目的のひとつでした。09年~11年にかけて、一緒に授業を作っている渡辺清高先生(※)をヘッドに『患者、家族、国民の視点に立った自立支援型のがん情報の普及のありかた』という研究を行いまして、その成果を発表する場として、放送大学を選んだのです。ここは生涯学習の拠点で、すべての世代の社会人が対象で、特に伝えたいと思っていた女性の方々に教えることができますから。
※帝京大学医学部内科学講座病院教授(肩書は2023年時点) -
麻木:田城先生や渡辺先生の思いが伝わる授業でしたし、私も実体験から理解が深まりました。
-
学びを通して理解できた物事の背景
-
麻木:授業を通して、物事の背景も理解できるようになりました。例えば私ががん治療を受けたのは10年前ですが、その後も診察のため、定期的にがんセンターに足を運んでいたんです。当初センターに足を踏み入れた頃は、かつらや、キレイに見せるためのメイク法などのコーナーが大きく設けられ、「ともに語り合おう」と患者会のポスターが貼られていました。
-
田城:抗がん剤治療や手術跡に対する、見た目のフォローが中心だったのですね。
-
麻木:はい。そこから徐々に大きな情報センターが併設されていき、「がんになっても、慌てて仕事を辞めないで!」という札と共に、ハローワークから出張相談窓口が来るようになっていました。つまりこの10年で、社会ががんにどう関わっていくかという“衣替え”を目にしてきたわけです。
-
田城:その変化にしっかりと気づかれたことも素晴らしい。
-
麻木:今回の授業を通して「なぜ衣替えがされたのか」がとてもよく分かりました。「こういう法的根拠があり、こういう研究成果があり、分析があって、だからあのような変化が起きたのか」「がんについて最先端で考える人たちがいて、研究成果があるから、社会や法律は変わっていくのか」と、私が漠然と見ていた事象に理屈が備わったんです。
-
田城:経験と学問を繋ぎ、物事の背景理解が深められるのが成人学習の面白さでもありますね。
-
麻木:はい、自分の感覚に論理がくっついてストンと腑に落ちる、とても楽しい経験でした。
-
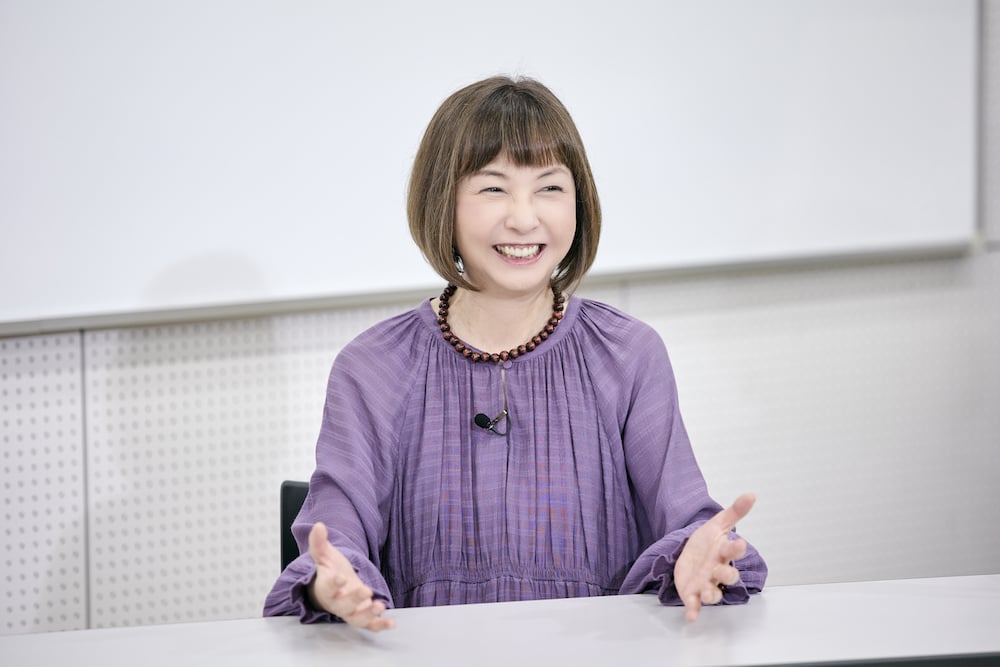
-
田城:おっしゃった仕事の部分に関して、授業ではがん患者の就労支援についても取り上げています。昔はがんになったら、仕事を辞めるという辛い流れがありましたが、今は治療のために仕事をすべて休むということは少なくなっています。例えば放射線の照射自体は5分ほどで済みますから、午前中に病院に来て照射を受け、午後から職場に出勤するという方はたくさんいらっしゃいます。薬の治療では吐き気が出たりしますが、その吐き気を抑えるためのステロイドが処方されたりもする。現在は、日常生活を阻害しないがん治療が可能なのです。
-
麻木:これまでと大きく変わらない生活が送れるというのは、心の平穏にも繋がると思います。
-
田城:そうですね、検診をきちんと受けて早期発見できれば、治療を受けつつこれまでと近い生活をし、がんとともに生きることができます。完治は難しい場合もありますが、がんで寿命が縮まるということは少なく、がんになっても長生きできます。しかも「大丈夫」という明るい気持ちでいると治療もよく効きます。がん患者で、しかも長生きしている方が多いということは医療現場のがん治療経験も豊富ということですから。
-
麻木:がんはありふれたものであり、やはり治る可能性も高いということですね。
-
田城:ぜひ、そのことを多くの方に知っていただきたいですね。ただそのためには、繰り返しますが早期発見・早期治療が必須です。
-
麻木:かつての私がそうでしたから痛感します。検診をしていなかったらと考えると…。
-
田城:まさに自覚症状がないうちに検診を受けるというのが、大事なポイントです。日本では諸外国に比べ、正しく検診を受けられていないというのが現状なので、それは今後の課題と言えるでしょう。
-
学びを通して見えてきた“問い”
-
麻木:授業を受けたことで、最近では新しい問いが浮かび始めています。それは「働き手ががんになっても、社会的に生きていくためにはどうしたらいいのか?」ということです。
-
田城:社会的に生きていくとはどういうことでしょうか。
-
麻木:私の手術は、3泊4日の入院で終わりまして、幸い仕事にほとんど影響もありませんでした。しかし、人によってはもっと長く手術や治療に当たらないといけない場合もあるでしょうし、数年単位という長い目で治療を考えていくことも必要になります。
-
田城:そのようなときは、会社も個人の事情を理解し、受け入れ体制を取らなければなりません。
-
麻木:一方で、私のようにフリーランスで働く人間は、がんになると治療のために仕事を休まざるを得ず、その間は無収入になるというように、がん対策基本法の恩恵を受けられずにいる人もまだまだ多くいます。授業でがんの研究が進んでいて、がん関連の法があると知ったからこそ、その恩恵からこぼれ落ちている人がいることが、とても気になっています。秋のピンクリボン月間になると、「検診を受ける人を増やしたい」と講演のご依頼を受けるものの、そもそも講演に来てくださる方はほぼ、がん検診に行っている方なんです。
-
田城:本当に話を聞いてほしい人、がん検診を受けてほしい人に届いていないと。
-
麻木:そうなんです! だから「身の周りの人を3人、検診に連れて行ってください!」と呼びかけています。また「職場でがん患者の方が出て治療のため休みを取っているときなどは、“お互い様”の精神を持ちましょう」ともお話しします。自分も、いつがん患者の立場になるか分からないわけですから。
-
田城:素晴らしいご活動だと思います。
-
麻木:がんとともに生きやすい社会というのは、介護しながら生きやすい社会、子育てしながら生きやすい社会、障がいがあっても生きやすい社会でもあると思います。だから“がんとともに生きる”は共助の精神、みんなで一緒に生きるということなのかなと気づきました。
-
田城:まさにおっしゃるとおりです。がんとともに生きる社会づくりというのは、地域共生社会、すべての病気や経済的困窮者、引きこもり、さまざまな障がいを負って困っている人を助ける社会であるということ。それには患者さん、家族、地域住民がみんな参画して考えていくことが重要です。がんの治療法は日進月歩で、今も進化し続けています。
-

-
麻木:先ほどの問いはがんからサバイブできるようになったからこそ生まれたのかなとも感じています。同時に「がんなんて、自分には関係ない」と思っている人にどう伝えればいいだろうかと、考えを巡らせるようになりました。
-
田城:がん対策基本法は2006年に山本孝史参議院議員(当時)の尽力により成立した法案で、山本氏が自身もがん患者であることを国会で明らかにしたうえで、「自分の目の黒いうちに、この法案を通してほしい」と願い、そこから数カ月で成立したという、非常に人間くさいドラマがありました。麻木さんのお話にあったように、正規雇用でない人々を支えるためには、NPOやボランティアなどと協力した新しい仕組み作りも必要かなと思います。弱い立場の人々が声を上げて、行政に届ける。また行政を待たずに自分たちで計画をし、実行していくということも必要かもしれません。
-
経験者だからこそ伝えられるもの
-
麻木:最近、とても親しい年下の友人が非常に進行の早いがんで亡くなったのですが、最後は自宅での緩和ケアを受けていました。私は緩和ケアに関してはあまり知識がなく、なんとなく「病院で亡くなるのが安心なのではないか」と思っていましたので、そうではないことに驚きましたね。
-
田城:本来はがんという診断がついた時点で緩和ケアがスタートします。進行性のがんの場合は、次第に治すための治療が限られてきますから、緩和ケアの割合が増えていきます。病院での治療と、在宅での緩和ケアを担当する医師は異なることが多いので、患者さんと緩和ケア担当医とのマッチングもできるだけ早いタイミングで行うことが重要です。ただ、日本人のメンタリティ的に「ゆくゆくはこの先生にお世話になります」という話をいつ、どう告げるかが難しいという問題もあります。
-
麻木:それと、一般的な認識では、「自宅に帰される=医療から見捨てられた」と受け取る人も少なくありませんよね。そうではなくて、フェーズが変わっていくのだという認識がまだまだ浸透していないし、そのシステムも全国津々浦々にまでは及んでいないという状況です。医療から見捨てられて家に帰るのではなく、「自宅で違うかたちでの治療を受けて人生を全うするのだ」「そのかたちを求めていいのだ」と一人でも多くの方に知ってほしい。有権者の人たちが自分事としてもっとがんのことを考え、自治体に働きかけていくことが大事ですね。私としては、この授業を受けたからには、授業で教わったたくさんの知識をどこでどのように発信していくか、しっかり考えていきたいと思っています。
-
田城:自分の体験を活かして周りの人に影響を与えるというのが、キャンサーサバイバーの方々の役割です。ご自身の経験を通じて、不安や心配を抱えているがんの当事者に「これはこういうことなんだよ」「こんなときは、こうするといいよ」などとアドバイスするのは、有意義なことだと思います。余談ですが、医者にどの病気で死ぬのがいいかと問うと、がんを選ぶ人が多いんです。
-
麻木:それはなぜでしょうか。
-
田城:自分の死期に心の準備をして向かえるからでしょう。今の医学なら、痛みは早いタイミングから抑えることができますし、痛みがなければ元気で食欲が増し、仕事などで身体を動かすこともできます。そうすると免疫が活性化され、がん細胞を抑えることもできます。
-
麻木:なるほど。それにがんと診断されても、これから先に新しい治療法や薬が出て、長生きできる可能性も大きくありそうです。
-

-
田城:そうですね。がんと分かったときに「あとどのくらい生きられるか?」を前向きに捉えて生き方を改めて見直すこと、そしてがんになった先駆者が一致団結してがん患者とその家族の助けになる制度を考えていけたらいいですね。麻木さんにもぜひ、声を上げる役割や情報発信を、これからもお願いしたいです。
-
麻木:制度からこぼれている人のほかに、中には制度があることを知らないために損をしている人もいるはず。そういった方もきちんとすくい上げ、全国津々浦々の方々があまねくケアを受けられるような社会のシステムができるといいなと、想いを強くしました。
-
田城:『がんとともに生きる』では、がん情報を正しく知るだけでなく、がんを経験した仲間とのサバイバーシップ、患者さんを支える看護のありかた、がん患者の家族支援などをこれからも伝えていきたいと思っています。ぜひその学びを活かし、ガンサバイバーとしての麻木さんの今後の幅広いご活躍をお祈りしております。
-
麻木:ありがとうございます。これからも学び続けていきます。
【田城教授プロフィール】
田城孝雄
放送大学教授
東京大学医学部保健学科卒業、同大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院第一内科助手、米国Michigan大学内科Research Fellow、東京大学附属病院医療社会福祉部助手、日本医師会総合政策研究機構主任研究員、順天堂大学医学部公衆衛生学講座講師を経て、2007年順天堂大学医学部公衆衛生学講座准教授、2011年順天堂大学スポーツ健康科学部健康学科教授、2014年より放送大学教養学部教授。専門分野は内科、公衆衛生学、地域包括ケア、医療提供体制、医療連携、地域再生、まちづくり。
