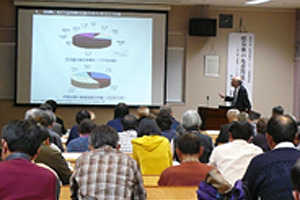| 学長メッセージ | 地域貢献への取り組み | 科目群履修認証制度 (放送大学エキスパート) |
面接授業 (スクーリング) |
地域貢献活動をする 学生の紹介 |
| 岐阜学習センター | 平成27年度 | URL:http://www.sc.ouj.ac.jp/center/gifu/ | ||||||
| プロジェクト名: 岐阜県の地震環境を理解する~迫り来る海溝型巨大地震による被害をどこまで下げられるのか~ |
||||||||
| 1.プロジェクト概要 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県における被害地震の歴史を概観し、そのうえで逼迫生の極めて高い海溝型巨大地震による岐阜県域に特徴的な被害の様相について解説する。そして、被害を如何にして小さくできるのかについて考える。また、実際に災害対応を行う岐阜県と高度教育機能・研究機能を持つ岐阜大学が共同して、防災・減災にかかる実践的シンクタンク機能を担う「清流の国ぎふ 防災・減災センター」の事業内容について解説する。
|
||||||||
| 2.プロジェクトの成果 | ||||||||
| 過去に岐阜県で起こった事例を取り上げることにより、巨大地震が遠い未来の話ではなく、いつ起こってもおかしくない身近な問題として認識された。 実際に高い震度の揺れが起こることで住宅がどのように倒壊していくのか、また、震災から復旧するためにはどの程度の時間を要するのか、を講師が具体的に示したため、地域社会で協働体制を築き備えることの大切さも認識できた。 本講演会には、一般市民で防災に関する役職を持つ者からも関心を持たれ、多数参加しており、減災センターと市民の接続にも役立ち、今後の市民向け防災教育の発展も期待できる。 |
||||||||
| 3.プロジェクトの課題 | ||||||||
| 今回のような防災に関するプロジェクトは、一過性に終わることなく継続することに意味がある。行政機関や教育・研究機関などの関係機関と連携し、地域の成人が多く所属する学習センターならではの地域貢献を引き続き行いたい。 | ||||||||
| 4.今後の展開計画 | ||||||||
| 本プロジェクトが地域住民に好評だったことが事後のアンケート集計結果により判明した。先日、内閣府より南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告が発表されたことを踏まえ、今後はより一層地域の特色を踏まえた防災に関するプロジェクトも計画したい。 | ||||||||
| 5.参加者の感想 | ||||||||
| この公開講演会に参加して、あらためて日本が地震大国であることを認識ができた。 講演会の内容の中で地球規模の地震発生を見た場合に、発生場所が限られ場所で死者の割合が大きく、復旧に長い期間がかかり、予測・予知が難しいことが理解できた。 歴史的に見ても地震が必ず発生することを認識して、過去の災害教訓を活かして減災にすべく教訓がいかされなかったのが疑問視するところである。 岐阜県での被害地震も歴史を見ても大きな被害があった。大きな地震が到来した場合、現在のインフラ社会維持することが難しいと感じる。また、相当の死傷者が発生する。 巨大地震が予想される中、私たちが協働で減災社会を構築する必要がある。県民、市民など地域共同体制の組織化を早急に作り上げるため官民一体で啓蒙活動を系統的に実践し地域共同の組織化と情報の共有化をしなければならないと感じた。 |
||||||||
| 6.写真 | ||||||||
|
||||||||