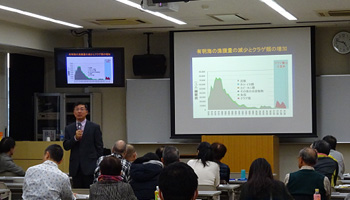地域貢献への取り組み
2019年度 広島学習センター
| 施設名 | 広島学習センター |
|---|---|
| 年度 | 2019年度 |
| URL | https://www.sc.ouj.ac.jp/center/hiroshima/ |
| プロジェクト名 | 広島の豊かな里海を守る人材育成プロジェクト |
| 1.プロジェクト概要 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
広島をはじめ瀬戸内地域では、人々の里海であり生活に大きな影響を及ぼす「瀬戸内海」の保全に活躍できる人材の確保が求められる。専門資格としては、技術士、調査士、計測士、管理士、カウンセラー等々多種あるが、「放送大学」が、これら資格のキャリアアップに寄与することを目的に、平成29年度に本事業「広島の豊かな里海を守る人材育成プロジェクト」を立ち上げた。令和元年度は4件の関連分野面接授業、1件の公開講演会(講演2件)、関連活動として1件の施設見学会を行った。また、研修旅行では瀬戸内海に生息する生き物が一般公開されている福山大学マリンバイオセンター水族館を見学した。 *関連ウェブサイトURL *実施体制(主催、共催、後援等) *事務局体制(人数等) |
|||||||
| 2.プロジェクトの成果 | |||||||
| 施設見学会では広島大学水産実験所を7名が訪問し、他大学との共同研究を行っている研究施設を見学し、公開講演会では46名が参加し、地球観測衛星を利用した海の生態系の研究とエチゼンクラゲの発生の研究について学んだ。面接授業でも海の動物を観察する宿泊実習を行い、また研修旅行では瀬戸内海に生息する約150種類の水生動物を飼育展示する福山大学附属の水族館を見学した。このプロジェクトを通じて海の現状を知り、海の恩恵に与る一人として「さとうみ」の保全とは何か、今後どう行動すべきかを考える契機になった。 | |||||||
| 3.プロジェクトの課題 | |||||||
| 3年間、施設見学会と公開講演会を毎年行い、学生は海の現状や関連する課題についてを学び、里海に対する関心は高まったが、プロジェクトが終了した来年度以降にどうやってこの関心を持続させ、里海を守るための人材育成にどのようにつなげるかが課題である。 | |||||||
| 4.今後の展開計画 | |||||||
| 学長裁量経費としてのプロジェクトは今年度で終了するが、里海に対する学生の関心を来年度以降も持続させるために、里海に関連した面接授業や講演会を計画していきたい。 | |||||||
| 5.参加者の感想 | |||||||
| <施設見学会の感想> 研究員の足立さんから、水産実験所のことと、研究してきた東日本大震災における海洋生物などの話を聞いた。日本にとって水産資源は、すごく重要である。東日本大震災後の水産資源の研究所、東北マリンサイエンス研究所では、震災前と後での生態系を研究しているそうである。理由は、震災後生態系が崩れて、ある場所ではウニが大発生したり、干潟が流失して失われたりしたからである。 震災後の復旧で、人工の干潟が作られたが、そこにもアサリなどの生物などが戻って来ていること、その生物はDNA分析をしても震災以前の生物と何ら変わらないことが、確認されたそうである。震災の影響が心配されたが、影響がなくて本当によかった。後は、徐々に昔のような海に戻ることを祈るだけである。 |
|||||||
| 6.写真 | |||||||
|
|||||||