学習センター所長
北海道・東北地方

私の専門は理論言語学とコミュニケーション論ですが、2000年代半ば頃から観光についての共同研究(観光創造)を開始しました。現在は、観光創造と平和研究の融合を目指して平和観光研究に取り組んでいます。既存の学問領域を架橋しながら領域横断的研究を実践してきたこれまでの経験を活かし、学習センターにおいても学生たちと現代社会のアクチュアルな問題について一緒に考えたいと思っています。

京都出身です。まず、青森県に当時の県立工業試験場に技術研究員として18年間奉職しその後,前任大学にプロダクトデザイン領域で採用され、15年間地域産業の産業デザイン研究に携わりました。さらにその間8年ほど全学のキャリアセンター長を兼務することもできました。これらの経験を生かし、放送大学では学びを求める皆さんと共に、これからの生涯学習の支援の一助になれれば幸いです。

専門は英語文学、とくにシェイクスピアをはじめとする英国演劇作品群とその社会的文化的背景などに関心があります。演劇作品における対話への関心は独白から詩へ、さらには小説の語りへと広がり、「語られないことが伝わるしくみ」についての興味にここ数年取り憑かれています。情報・情緒は言語を媒介として共有されます。ことばを磨くことを通じて、みなさまの学びに寄り添いたいと考えています。

日本教育史を専門領域にしております。とくに、近世から明治期にかけての、民衆の読み書き教育について研究してまいりました。近世の日本においては、国家的な民衆教育政策といったものは、ほとんどありませんでした。にもかかわらず、一般民衆を含む多様な階層に読み書き教育が普及したのが、近世という時代でした。近代的な学校教育によってそのあり方が大きく変わっていくことになりますが、その変容の過程についても、興味を持っています。放送大学における学びは、なによりも自発性にもとづいて成立するものだと思います。その学びができる限り達成されますよう、その支援に尽力して参りたいと思います。

群馬県伊勢崎市出身です。専門は電子工学で、大学院生時代の半導体技術の開発から研究をスタートし、高周波素子の開発研究や、テラヘルツ波の応用研究等を行ってきました。最近では、カーボンニュートラル等で地方創生につながる研究の創出等に取り組んでまいりました。これまでの教育・研究とマネージメントの経験を活かし、秋田学習センターの発展と、学びを求める皆様の生涯学習の支援に役立ちたいと考えております。

2024年10月に山形学習センター所長に就任しました。放送大学とのご縁は長く、1988年から面接授業担当や客員教員をしばしば務めました。日本近世文学専攻ですが近年は日本文化(「世間」と「社会」/日本文化の国際化)も研究範囲です、教育・社会連携としては「NIE」(新聞を活用した教育)、日本語によるアカデミック・ライティング、高校の探究学習支援に取り組んでいます。

専門研究は、社会教育・社会教育実践を通して学習者が進める主体形成の展開過程を<対話的>な学習の観点から分析・検討することを中心としました。特に東日本大震災以降は「地域と教育の復興」をテーマとしています。震災復興には、地域の未来創造への市民の主体的参画とそれを可能とする市民の<学びあうコミュニティ>の形成が不可欠です。放送大学の果たす役割の一つがそこにあると期待しその発展に努力して参ります。
関東地方

茨城学習センターは水戸市にあります。水戸徳川家9代藩主斉昭は「一張一弛」の理念で、弘道館と偕楽園を設けました。15歳から入学できる藩校弘道館は、当時最大規模の総合大学でした。弘道館では幅広く学識を培い、時に偕楽園でなごむ。この一張一弛の理念は、生涯教育も担う放送大学の理念と相通じるものがあるように思います。目的を持った皆さん個々の、学びとゆとりを支援していきます。

専門分野は発育発達で、就学前の子どもから高校生までの運動技能の発達について研究してきました。体力テストのようなタイムや距離などの結果だけでなく、走り方や投げ方などの運動の仕方がどのように向上していくのかを明らかにすることに取り組んでいます。今後はこれまでの経験を生かしてスタッフ、客員教員の皆様とともに栃木学習センターの運営・発展に貢献できるよう努めて参りたいと思います。

専門分野は「物理化学」の中の「計算化学・理論化学」で、これまで主に高周期第14族元素や遷移金属元素を含む多様で新奇な分子の物性を、コンピュータを用いた量子化学計算や分子動力学計算を用いて研究してきました。前任大学では、上記の研究や教育の他、男女共同参画やダイバーシティ推進事業にも携わりました。放送大学群馬学習センターでの職務にこれらの経験を活かしていければと考えております。

専門は憲法学です。とくに、ドイツの憲法裁判制度を素材に、より効果的に人権を保障できる裁判の在り方を考えてきました。あわせて、一人一人の個人が尊重される社会についても考えています。放送大学は、時間や場所に制限されることなく、学問の自由を実現できる場所です。前任の大学で運営に携わった経験を活かして、学習センターでの学生のみなさんの学習、研究のサポートができれば幸いです。

健康教育が効果をあげる上で重要な意味を持つ保健行動理論を主要な研究領域としてきました。その中でも特に自分の行動、思考、感情をコントロールするスキルに関心があります。社会的活動としては、養護教諭や保健体育教員の養成、小学校から高等学校までの保健体育の教科書づくりなどにかかわってきました。放送大学の多様な学生と交流し、ともに学ぶことを楽しんでいます。

専門は情報通信工学です。特に、シャノンによって創始された情報理論の研究を行なってきました。前任の大学では、学生支援センターのキャリア支援部門長を長年務めた他、学内の情報ネットワークの整備や情報セキュリティ対策を行っていました。これらの経験を活かして、学習センターの学生の皆さんの学びをソフトとハードの面からサポートしていきたいと思っています。

2023年4月から東京文京学習センターのセンター所長を務めています。教員生活を通じて西洋倫理思想史に関する講義・ゼミを担当する他、主としてドイツ・フランスの哲学・倫理学をめぐる研究の傍ら、日本近世や近代の思想家、文学者について勉強してきました。学生の皆さんの修学のお手伝いが出来れば、と考えています。

私の研究分野は動物生理学及びバイオメカニクスです。生物の運動能力に注目してきた研究の過程で、動物の行動を含めた生命現象と地球重力との関係に興味を持ち、日本の黎明期の宇宙実験に関わり、スペースシャトルなどによる軌道上実験や、航空機を利用した無重力実験を行ってきました。今までにないアプローチを行うことで見えてくる、生命科学の新たな発展の可能性について考えていきたいと思います。

東京生まれ。専門はスポーツ社会学です。「いつでも、どこでも、だれでもがスポーツを」の理念を支える政策や制度について研究を続ける中で、全国の地域でスポーツに関わる多くの方々の生き生きとした姿を目にしてきました。私自身は地元の市民オーケストラでヴァイオリンを弾き続けて40年。学習・文化・スポーツ活動は、人々に活力を与え、日々の暮らしを豊かにしてくれるとの思いの元、学習センターでのみなさんの学びのサポートに努めてまいります。

専門は化学物質のリスク管理です。新型コロナ禍や自然災害など普通に生活していてもリスクを意識せざるを得ない時代となってきました。これからはリスクと共生した社会を創造する時代だと思います。神奈川学習センターには多数の学生の皆さんが所属されています。学習センターでの面接授業などで多様な社会を経験しながら学生の皆さんが充実した大学生活を送れるようにサポートしていきたいと思います。
北陸・甲信越地方

専門は宇宙物理学の理論的研究です。最近では,大型重力波観測計画であるKAGRAプロジェクトで,データ解析やデータ共有に関わるソフトウェアの開発・整備,コンピューター環境の管理・運用などを行ってきました。新潟学習センターでは,これまでの教育,研究の経験を活かして,多彩な経歴を持つ様々な年代の皆さまに「学ぶ楽しさ」を知っていただけるよう尽力していきたいと思っております。

経営学、比較経営を専門にしています。私たちが暮らす市場経済下での企業経営と計画経済下での企業経営の差異について研究しています。後半部分は放送大学の学生さんも含めて皆様の生活とあまり関係がない領域ですが、ここを知ることによって市場の役割を認識できるかと思います。これからは専門領域とは関係なく、放送大学の重要な役割である生涯教育の拡充に少しでも貢献できるように努力いたします。

石川県の金沢に生まれ、金沢大学で41年間教育・研究に携わってきました。専門は有機合成化学で、特に糖類の環内酸素原子を同族のイオウやセレンに置き換えた擬似化合物の新しい合成法を開発してきました。石川県には数多くの伝統文化が残されており、生涯学習としてこれらの魅力も含めて石川学習センターより提供できればと考えています。スタッフの皆さんの力を借りて私も一緒に学んでいきたいと思います。

大阪府の出身です。専門は数学で、より詳しくはアフィン代数幾何学に関連する可換環論というものを研究しています。前任の福井大学では、36年間にわたり教育と研究を行ってきました。実に長い間、教育に携わってきたことになりますが、同じ内容でも教えるたびに新しい発見があり、面白さとともに教育の難しさも痛感しています。そのような経験も生かしながら、学習センターを通じて放送大学に少しでも貢献できればと考えています。

山梨県笛吹市生まれです。専門はデザインで、大学院修了以来40年の間、教育・研究に携わっています。前任の山梨大学では、28年にわたる在職中直近の7年間、キャリアセンター長、教学担当理事、教育国際化推進機構長、学生サポートセンター長など、学生支援を中心に大学運営に従事してきました。これらの経験を活かし、山梨学習センターの円滑な運営と放送大学で学ぶ方々の学びの充実に貢献したいと思います。

専門は地質学、とくに野外に出て地質を調べ、地質構造とその形成プロセスを明らかにする構造地質学にたずさわってきました。山国信州にあって、最近では内陸地震を引き起こす活断層と地質関連災害を扱っています。これまでの共通教育と専門教育の両面における経験を基に、ますます重要になるスキルアップや教養を高めるため、学びの場をより効果的に皆様に提供できるよう努めてまいります。
東海地方

出身は青森県弘前市です。札幌で大学生活を過ごし、岐阜大学獣医学科の教員となりました。専門はウイルス感染症学および人獣共通感染症学です。ウイルスが動物に病気を起こす仕組みを明らかにすることで、病気の制圧を目指しています。大学時代には地(知)の拠点事業に参画し、県内の自治体との連携にも関わることができました。これまでの経験を活かし、放送大学で学ぶ皆さんの学習支援に取り組んでまいります。

出身は岐阜県大垣市で、東京での学生生活を経てここ静岡で人生の半分以上を過ごして来ました。センターのある三島市は水の豊かさという点で生まれた街とよく似ていて、一種のなつかしさを感じています。専門は哲学で、最も敬愛する哲学者はオランダの哲学者スピノザです。同時代の画家フェルメールの絵のような彼の静かで、しかし確固とした世界観にいつも魅了されています。

経済学が専門です。中高の社会科で出てくる需要・供給曲線図を見て、具体的にリンゴの需要・供給曲線はどうやって描くのか興味を持ち、経済学部に進みました。研究は計量経済学の手法を用いる生産性分析で、特に公益事業の規制と自由化に関わる実証研究を行ってきました。前任校で異分野融合的な教育と研究の取組みにも関わった経験を活かし、皆様に自由闊達な学びの場を提供できるよう努める所存です。

三重県津市出身です。専門は栄養化学・薬理学・生化学で、細胞内情報伝達や細胞増殖に関わるタンパク質の機能、および食品成分の生体調節機能に関する研究を行ってきました。山の頂から海の底までの幅広い領域を教育・研究フィールドとする農水系の研究科に在籍していた経験を活かし、三重学習センターのスタッフの方々とともに学生の皆さんの学習を支援していきたいと考えております。
近畿地方

会計学、とくに財務会計論を専門としています。学部学生時代より、ドイツ会計学を研究してきたこともあり、実務に発露する会計事象を収益費用観(シュマーレンバッハにより確立された動態論)の立場から、どのように説明することができるかということを中心に研究を続けています。また、公認会計士の試験委員等を務めていたこともあり、前任校では、資格取得を希望する学生への指導にも努めました。そうした経験もふまえて、滋賀学習センターでは職員の方々の協力を得ながら、皆さんの学習をサポートしていきたいと考えおります。

私は岐阜市郊外の農家に生まれ、山村で育ちました。法学部で政治学を学び、東南アジアの政治を研究しています。タイが専門で、ここ10年ほどは民主化を妨げる要因として君主制、軍隊、司法機関に着目し、地域研究のアプローチから実態の把握と分析を行ってきました。これまでの経験を生かしながら、皆さんの学びのお役立てればと思います。

大阪市の出身です。日本語学、特に文法を中心とする日本語史と、「役割語」について研究してきました。役割語とは、「わしは知っておるんじゃ」と言えば老人、「わたくしが存じておりますわ」と言えば上品な女性、といったように話し方の属性と深く結び付いた話し方のことです。今後は客員教員、スタッフのみなさんとともに、大阪学習センターの発展に努めたいと思います。

島根県松江市出身です。専門は加齢の身体運動科学で、高齢者の転倒予防に関わる研究とwell-being(ウェルビーイング)の実現を目指した地域コミュニティ介入研究を行ってきました。兵庫学習センターからは、人・もの・情報が行き交う拠点である神戸港を眼下に望むことができます。学習センターが多くの皆さんの"自由な学びの港"となるよう、スタッフの方々と力を合わせて頑張りたいと思います。

専門は中国文学、特に明清の詩文です。漢詩漢文には堅苦しいイメージがありますが、研究の中心は、中国文学にはどのように女性や子どもが描かれてきたかということです。私が大学院に入ったのは学部卒業から6年後。定時制高校教員との二足のわらじで大忙しでしたが、今振り返ってみると、誰に強制されたわけでもない学びの時間は人生最大の愉悦の時でした。この学びの愉悦を味わうお手伝いをしたいと思っています。

大阪府堺市出身です。専門はインターネット応用のグループウェアという分野で、発想支援、遠隔授業、IoTなどの研究を行ってきました。和歌山学習センターは著名な建築家である渡辺節氏設計の松下会館の中にあります。ここから、自然・文化の豊かな和歌山の情報を面接授業で発信していきたいと思います。そして、皆さんが気軽に集まれる拠点をめざしたいと思います。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。
中国地方

私は食品・栄養科学を専門としております。特に、植物性食品、例えば野菜や果物には含まれないが、魚介類を含む動物性食品に存在するビタミンB12に関して、その分析方法と体内での機能について、40年間研究を重ねてきました。鳥取学習センターでの客員教授としての3年間の経験を生かし、皆様の夢や目標達成に向けて共に成長し、未来に向けて一歩ずつ進むお手伝いをさせていただきたいと考えております。
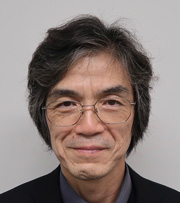
島根県出身です。専門は文化人類学で、構造主義という人類学理論の研究と、スウェーデンを中心に北欧の国際養子縁組の調査研究を行ってきました。北欧で出会った国際養子家族の人たちは、家族にとって生物学的関係が全てではないことを教えてくださいました。島根学習センターでは、スタッフの皆さんと共に、日常の当たり前を見つめ直す手がかりを提供できればと考えています。

専門は日本の中世文学で、とくに院政期から鎌倉時代初頭にかけての和歌文学に関心を抱き、『新古今和歌集』や藤原俊成・定家等の歌人について研究して来ましたが、この時代の和歌は王朝物語とも深い関りがあるため、『伊勢物語』『源氏物語』に代表される平安時代の物語文学にも興味を持っています。縁あって30余年ぶりに本学に勤務することになりましたが、皆様とともにさらに学びを重ねたいと願っています。

専門分野は農学・動物生産科学で、鳥類の健康と生産物の安全性を高めるための感染防御機能を研究しています。農業生産は技術開発、地域の特性、社会情勢などを総合的に考えることが必要です。皆さんも、目指す分野は多様ですが、課題に対していろいろな視点から総合的に対応できる力を高めていただきたいと思います。これまでの教育研究の経験を活かしながら、皆さんの学びを支援していきたいと考えています。

神奈川県出身です。専門は運動生理・生化学で、骨格筋の可塑性について研究してきました。最近では、骨格筋は運動だけではなく、健康の保持にも大きく関係していることが明らかにされつつあります。常日頃、自身の体の変化を目の当たりにしながら、骨格筋の萎縮抑制や萎縮からの回復を促進する方策に興味を持っています。今後、これまでの経験を活かし、スタッフの方々と共に山口学習センターの運営・発展に貢献できるよう努力して参ります。
四国地方

専門は電気電子工学の中の電子回路工学で、主として電子回路の高信頼化法に関する研究を行ってきました。また電子回路のモノ作りの教育にも力を注いできました。前任の大学でのその研究と教育での経験を活かし、徳島の地域文化の振興にも携わりながら、学生さんとともに生涯学習の一拠点となるよう努めてまいりたいと思っています。

2025年4月より香川学習センター所長に着任しました山神眞一と申します。同年3月まで香川大学で43年間勤めていました。専門分野は、スポーツ医学的見地から探究する運動学です。これまでに5年間香川学習センターの客員教授としての経験がありましたが、今後は、学び続ける人生100年時代の生涯教育の推進を目指して、自らの経験を活かした放送大学の活動に邁進してまいりたいと思っています。

専門は西洋近現代史です。両大戦間期イギリスの金融政策史から研究を始めて、近年ではイギリスにおける第一次世界大戦の戦死者追悼の問題を、地域のアイデンティティ形成と関連付けて研究しています。また、四国の地域文化である四国遍路の研究に、「世界の巡礼」研究担当として、参加してきました。愛媛の地域文化を大切にしながら、地域の学びの拠点である学習センターの発展に尽力したいと思います。

専門は水圏生命科学です。魚類の必要な栄養や体内での代謝を他の動物と比較しながら魚の特性を調べて養殖魚の育成に役立てる研究をしていました。おかげでフィールドに出る機会が多く地域の自然環境に目を向けることができました。この経験を元に、高知学習センターが地域の文化と自然を活かした魅力的な地域の学びの拠点となりますようセンターのスタッフとともに尽力していきたいと考えています。
九州・沖縄地方

愛媛県西条市の出身で、祭りの盛んな土地に生まれ育ちました。専門は生物無機化学です。私達の身の回りにあって生命活動に大きな役割を果たす金属錯体の構造や機能を探求し、自然を超えた新しい触媒(バイオインスパイアード触媒)の開発やその利用について研究してきました。やや硬い研究分野の出身ですが、祭り好きでのんびりした人間です。これまでの研究や教育の経験を生かし、放送大学での学習がより楽しく、有益なものになるように、学生さんをサポートしていきたいと思います。

専門は人文地理学(都市地理学)です。都市を拡がりを持った空間として捉え、都心部の持つ機能や構造を水平的・垂直的な視点から解明を試みてきました。近年は地方都市の中心市街地の再生に力を注いでいます。学習センターの面接授業ではフィールドワークを取り入れ、みなさんと一緒に街を歩きながら今後の中心市街地の在り方を考えていきたいと思います。

専門は、電気電子工学です。主に、放電と絶縁に関する研究やパルス・パワー応用研究などを行ってきました。前任の大学では産学官連携、環境・施設部門や生涯学習センターのマネージメント業務に携わってきました。これらの業務を通して広く企業や学協会あるいは行政および自治体ともかかわってきました。長崎学習センターではこれらの経験を活かして幅広い活動を実施していきたいと考えています。

分子生物学、特にRNAの新たな機能に関する研究を40年以上進めてきました。研究室からは、150名を超える卒業生を社会の様々な分野に送り出してきました。学生達は、主体的に自分で考えて行う研究を通して、こちらが驚くほど、いつも大きく成長して社会に羽ばたいていきました。学習センターでも、学生に寄り添い、学びの支援をしていくことで、生涯に渡って成長していく手助けをしたいと考えています。

広島市生まれです。専門は統計科学です。修士課程修了後,広島・長崎の放射線影響研究所で原爆被爆者の方々の健康調査に関する統計解析に関わっていました。その後大分大学に移り,医学・生物データの統計解析手法に関する研究を中心に教育・研究を行ってきました。今後,大分学習センターでは,これまでの経験を活かして,スタッフと共に,学生の皆さんの学びをしっかりと支援してゆきたいと考えています。

専門領域は美学・美術史、美術教育です。日本の美術論である画史・画論や、それらの英米等における受容に関する研究を続けています。また、20年ほど前から、宮崎県内の有形文化財の調査に関わってきました。長らく前任校で担当してきた学芸員資格関連科目の経験も活かしながら、生涯学習の一環として、地域文化の発信や活用に関わる学びを支援していければと考えております。

専門は、中国文学で、特に唐代・宋代の文学を中心に研究しています。また、鹿児島県、沖縄県をフィールドに、薩摩、琉球の歴史研究や文献調査、フィールド調査も行ってきました。最近は特に南西諸島の博物学を研究対象としています。そのため、中国学ばかりでなく、地域研究についても様々なアドバイスができるかと思います。これまでの経験を基に、地域の豊かな学びを支えていきたいと考えております。

大分生まれ福岡育ちです。琉球大学で35年間、教育研究を行い、大学行政にも携わりました。専門は食品分析学で、沖縄特産農産物のフレーバー特性や機能性成分の解析に関わる研究を行ってきました。沖縄の伝統文化や観光産業、地域づくりなどに関連する分野についても、これらを学びのテーマとして学生が深く掘り下げることで高いスキルを習得し、地域社会での活躍につなげていくことに貢献したいと思います。




