すべての教員[50音順]

修士課程・博士課程と米国の大学で修め、情報技術と人間及び社会との関係性について研究をしてきました。放送大学着任以前は、ハワイ大学でコミュニケーション学を、ロチェスター工科大学で情報技術論を、ボストン大学で研究法を主に教えていました。帰国後、メディア教育開発センターでeラーニングに関する研究を、そして、現在では、広く技術の社会的影響に関心を持っています。

神奈川県出身。数理工学を専攻し、学生時代は脳の数理モデルをテーマにしていました。研究放送大学では ICT を用いた双方向の学習環境の構築に取り組んできました。現在は生涯学習における ICT を活用した学びの環境づくりについて関心を持って研究を行っています。

工学部の学生時代、ものづくりに携わったことでその奥深さを知りました。技能やデザインのように、これまでは人間の勘や経験に頼っていた物事を、データと機械学習に基づくやり方で再現し、ヒューマンコンピュータインタラクションの新たな展開を目指します。

中・高の教員を経たのち、短大、女子大学において食品学、栄養学、調理学など食物分野の授業を担当していました。その後、大学の農学部にて研究と教育に携わってきました。研究領域は食品科学ですが、遺伝子工学、分子生物学、生理学、分析化学などの幅広い分野の研究手法を用いて、味の伝わるしくみや味物質の設計について研究をしています。 “Health & Gastronomy”をキーワードに研究を進めています。

学部生の頃核融合に興味をもったことが、高密度物質を対象に理論物理の研究をはじめるきっかけとなりました。当初、天体プラズマ、原子核物質、クォーク物質と研究対象の密度は上がる一方でしたが、最近は低密度化が一気に進行し、冷却原子気体も重要な研究対象となっております。

千葉県出身です。函数が解になる微分方程式に興味を持ったことがきっかけで、解析学の研究を始め現在まで至っています。数理科学の中には、 函数方程式で記述される現象が沢山あります。 皆さんも一緒に考察してみませんか。

札幌は石狩川河口近くの茅屋に居を構え、夏はオフロードバイク 、冬はスノーボードに現を抜かしながら、肩肘張らずに「晴れ時々仕事」「全て楽しんだもん勝ち」がスタンス。夏の暑い日に飲むキンキンに冷えたソーヴィニヨンブラン、メンチカツ、松島花が好き。

長く児童思春期を中心とした臨床現場を渡り歩いてきました。悩み苦しむ子どもたちが一人でも少なくなればという思いでやってきましたが・・・前途多難な道が続いています。

長く研究所を中心に活動し、神経科学の研究に携わってきました。同時期、常勤や非常勤で精神科の医療施設で診療も続けてきました。そのようにして病棟と研究室を行き来するうちに、脳と心の関係に興味をいだくようになりました。脳は心の一部でしかない。ヒトが健やかな心を保つには物語を生きる必要がある。そんなことを臨床と研究を往復するなかで思いついたところです。

教育社会学を専門とする恩師から国の発展における教育政策の意義を説かれ感銘を受けて国家公務員となり、国立教育政策研究所に研究官としてしばし籍を置きました。成人教育に関する研究とともに自治体等の政策評価などの仕事にも従事しております。

佐賀県出身。教育社会学の視点と方法を基礎として、現代的諸課題に取り組んでいます。生涯学習と遠隔教育、才能教育、高等教育などが最近のテーマです。相互の関連は全くなさそうですが、実は大学をキーとして密接に関わる諸テーマなのです。

倫理学・日本思想・実存哲学が専門です。禅・芸道・武道等の修行によって開かれる世界に関心を持っています。また存在への問いにより古代以来の西洋哲学を克服し「新たな原初」への移行の準備を目指したハイデガーを研究、後期の「放下」は現代文明への根源的な批判であり、日本の思想に通じるところがあります。東西に学んで、新しい哲学を共に考えたいと思っています。

学歴:北京大学卒業、広島大学社会科学研究科博士課程(文部省国費留学生)職歴:中国社会科学院外国文学研究所、放送教育開発センター助手、メディア教育開発センター准教授、教授、放送大学教授。Stanford University School of Education(1996)、 The University of Pennsylvania Institute for Research on Higher Education (1999-2000)(文部省在外研究員)

思考、学習、知覚、運動制御の情報処理メカニズムの解明を目指し、実験とモデル構築に基づく研究を行っています。特に、違和感や協和感のような曖昧な感覚が生じるメカニズムに興味があります。また、情報通信工学への応用にも取り組んでいます。

生まれは京都ですが7か月で東京に引っ越してきたので東京育ちです。アメリカの現地校に行った1年間も含めて幼稚園から高校まで私立校に通っていたので、制服歴もお弁当歴も14年間でした(実は給食経験がありません)。放送大学は私の初任校です。

カナダ極北圏のイヌイトを中心に北米先住民の社会・文化を臨地的に研究してきましたが、人類学の理論一般についても強い関与と関心をもっています。

東京出身です。地球内部の岩石推定ソフトの開発と野外調査・変成岩成因論から研究を始めました。その後,岩石-水反応と地震や表層環境・生命活動などとの関連を研究してきました。最近は,遠隔教育における実験実習の方法についてもごそごそやっています。

長年、特別支援学校や教育センターで障がいのある子どもの教育や相談を行ってきました。また臨床心理士として小・中・高等学校で心理面に課題のある子どもの支援を行ってきました。本学ではその経験を生かし障がいのある学生の修学上のサポートをしています。

広島県出身。コンピュータやインターネットを活用して教育を改善する研究開発をしています。学びとは実践のコミュニティへの参加の過程であるという状況的学習理論の立場から、協調学習の支援と評価の問題に取り組んでいます。

ある場所に生息、生育する生物群集が、その環境条件に応じてどのように変化するのかを、人間の活動が生物に及ぼす影響に特に注目しつつ研究しています。研究手法としてのデータ解析法(特に多変量解析)にも関心を持っています。

障害法や国際人権法などが専門分野です。国際人権法は人権関係の条約などを対象とし、障害法は障害者関係の法を対象としています。どちらにも共通する研究対象として、特に障害者権利条約と差別禁止法を研究しています。障害者権利条約の内容が日本においてどのように実現されているのかを他国の場合と比較しながら検討しています。また、差別とは何か、差別をどう防止するか、差別をどう是正するか、などを考えています。

専門は政治学、なかでもモンテスキューやルソーなど、近代ヨーロッパの政治思想史を中心に研究しています。近年は、国家や国家間関係をめぐる国際関係思想にも関心を広げています。放送大学・東京都立大学法学部・東京大学法学部で研究・教育活動を重ね、2025年春に再び放送大学に着任しました。フランスの歴史や政治、フランス文化一般にも興味があります。

東京都出身です。専攻は、ヨーロッパ中世史です。特にネーデルラントを中心とする都市と宮廷の社会史的研究を行っています。

群馬県出身です。大学では、生理/生態学・メカトロニクス・環境情報学を専攻する研究室に所属していました。人の行動や生理情報および環境の変化を記録し,時空間情報として,ウェルビーイングの視点から生活に応用する研究をしています.

自然現象が数少ない自然法則で記述されることに感動し、理論物理学の道へ進みました。特に量子力学に基づく物質世界の記述を研究対象にしています。

専門は社会学/都市社会学。いわゆる「ホームレス問題」などの現代都市の貧困問題への社会的な対応のあり方について主に社会学的観点から実証的な研究を行っています。

長年、主に「遊戯療法」や「箱庭療法」の実践を通して幼児期・児童期・思春期の子どもたちを関わってきました。子どもがセラピイ場面で「遊び」や箱庭等に表現されるイメージを通して、どのように成長していくのか、その過程に興味があります。

長崎県出身。数学の特質の一つに、その論理性が挙げられます。数学という学問を外から見たときに、どのような論理構造になっているか、そんな基本的、根源的なことにだんだん興味が移っていき、いわゆる数理論理学、数学基礎論という分野が専門となりました。

1982年生まれ。2013年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)。専門は経済思想と環境思想です。経済学という知が人間の経済と生態環境との複雑なつながりをどう捉え、あるいは忘却してきたのか、また両者の持続可能性は今後どのようなものとしてありうるのか、広く社会思想や科学技術の歴史も視野に入れて研究しています。

滋賀県出身。京都大学大学院教育学研究科博士課程修了。教育学博士。京都大学名誉教授。臨床心理士・公認心理師。研究テーマは「もう一人の私」。個人療法を基本にしつつ、教育・司法・産業など、様々な場でおこる「心」の問題に関わっています。

「近くて遠い」中国の人たちのものの考え方に興味を持ち、11世紀宋代の歴史から勉強を始めました。宋代から編まれ始めた「地方志」という書物を研究するようになり、「どうして(地方の)歴史を作るのだろう?」と疑問を持ち、東アジアの史学史に関心を広げました。今は世界全域で作られる地方を描く書物の比較研究、「地方史誌学」を興そうとしています。

公立小学校教諭を経て大学教員となりました。大学での研究及び教育のほか、自治体の教員研修や学校研究・授業づくりの指導助言を行っています。また学校現場を研究のフィールドとして教育委員会、学校、企業との共同研究を進めています。近年は情報活用能力育成のためには、どのようなカリキュラムであるべきかについて関心があります。

日本中世史、特に鎌倉時代の政治史を専門に研究しています。史料編纂所に34年間在職し、「大日本史料 第五編」を9冊刊行しましたが、収録できたのは1248年10月から1251年7月までの35か月間分です。可能な限り網羅的に史料を調査するという仕事をしてきました。細部まで徹底的に探求するとともに、それを大きな視野に位置づける研究を心がけたいですね。

これまで、幼児の映像認知、バーチャル空間、博物館展示、ミクストリアリティ、視線計測、映像制作技術等、映像メディア関係に携わってきました。放送大学は面接授業の他に多様なメディアを利用した授業が特長です。今後もこの先駆的な研究開発を推進します。

新潟県出身。私たちは企業社会で生きています。そのプレーヤーである企業をよく理解することは、私たちの生活をよりよくするための糸口を与えてくれるでしょう。その鍵を握っているのが簿記・会計です。皆さんの受講をお待ちしております。

国や地方自治体の教育政策や教育行財政システムに関する研究をしています。これまでは学校統廃合政策や教師教育政策の研究をしてきました。また共同研究では教員の働き方改革,アメリカの教員スタンダード政策,過疎自治体の学校教育などのテーマに取り組んでいます。

アートセラピーを中心としたイメージ表現をベースに、医療や教育分野での心理臨床に携わってきました。同時に、日常と専門相談のはざまにある支援と、個々人の表現を生み出す場の理解をライフワークとしています。

東京都の出身です。これまでメディアリテラシー、メディア教育、教材開発、映像評価や授業評価支援ツール、リメディアル(学習のやり直し)教育などについて研究してきました。一方で、情報ネットワークやデータベースなど情報基盤の授業も担当しています。

生活保障の観点から、家族と国家の関係を問う研究をしてきました。家族というプライベートな領域で生じる問題が、その背後にある社会の制度・政策とどのように関わっているのか、という問題関心から、家族政策の研究を進めています。

1983年生まれ。2013年慶應義塾大学大学院法学研究科後期博士課程修了。博士(法学)。専門は国際政治学と日本政治外交史です。現在は戦後日本のエネルギー資源外交及び対外政策関係機構の変遷、初期の主要国首脳会議を中心に研究を進めています。

長らく教員養成系学部や教職大学院で教育心理学関係の授業を担当していた関係で、幼稚園児から大学院生まで教えた経験があることがプチ自慢です。住居が大学とは少し離れているため通勤時には春の桃の花や桜、秋の紅葉と、車窓からの風景を楽しんでいます。

日本史学は、古代史・中世史・近世史・近代史の四つの専門分野に分かれています。私はこのうち、近世史(16世紀後期~19世紀中期)を専門としています。主な研究テーマは、近世の都市社会の構造について検討する都市社会史です。

放送大学では、データ構造、アルゴリズム、プログラミング等のCSの基礎となる授業科目を担当しています。

秋田県出身。教育学部保健体育科修了後、博士課程では工学部情報工学科へ進み,医用工学を学びました。現在専門としている運動生理学分野に戻ってくるまでの間に経験した数々のことが、今現在の自分の研究に生きています。一つも無駄なことはなかったなと思います。

修士課程を終えてから長年精神科病院の現場で心理職として働いていました。心の健康問題により休職した労働者の復職支援や,対人恐怖とも関連の深い社交不安症,慢性疼痛と呼ばれる長引く痛みの問題などに対する心理療法の実践と,研究を行ってきました。

認知心理学の問題解決や文章理解をテーマに、研究を開始しました。最初の就職先が日本原子力研究所で、中央制御室の運転員の認知過程を研究しました。その後幕張の放送教育開発センターに異動し、現在に至ります。2017年度までは、情報コース所属でした。

盛岡生まれ仙台育ちという“お上りさん”ですが、思えば東京暮らしも40年を超え、自分の“内なる東北人”もだいぶ小さくなりました。当初は音声・音韻研究者でしたが、ある頃から、人は言葉で何をやりとりしているのか?を考えるようになり、今に至ります。

急速な社会の高齢化による介護の問題や、地域の医療崩壊の危機を乗り越えることが出来るように、保健・医療・介護・福祉に関する課題・問題について、理性的、合理的に考え、自分が住んでいる地域社会(コミュニティ)で自律的に行動できる市民・専門職を育成することに貢献したいと考えております。

数学科出身で数理論理学を研究していました。一方で、情報倫理や情報セキュリティなど、情報学と人間の関わりについても興味を持っています。雑学が好きで、広くいろいろなことを知り、そして、考える事が大事という主義で、日々、生活しております。

北海道出身。主として銀河や巨大ブラックホールの誕生と進化の研究をしてきています。暗黒物質(ダークマター)の宇宙における分布や、銀河の織りなす宇宙の大規模構造の研究もしているので、広い意味での観測的宇宙論が専門分野になります。とはいえ、太陽系の起源などにも関心があるので、天文学全般について皆さんと勉強を進めていけるよう配慮いたします。

石川県金沢市生まれ。都立大学の学部を卒業後、東京大学の大学院に進学、都立大学から博士(社会学)の学位を取得。主に都市における住民生活と自治体政策との関連について社会学的な調査研究を行っている。主著として『東京のローカル・コミュニティ』東京大学出版会、『創価学会の研究』講談社学術新書、『実践社会調査入門』世界思想社などがある。

埼玉県出身。Webの技術を用いた教育・学習システムの研究開発、そしてシステムの実践的な教育利用及び高等教育における調査研究を行っています。

かつて博物館で出会ったことをきっかけに、アンデス文明の研究を志しました。ヒトがモノに、モノがヒトに、相互にどのように働きかけ、時間の経過とともにどのように変化してきたのかを、道具や建物といった遺されたモノの分析から実証的に解明しようとしています。また博物館・美術館という装置に対しては、モノを残すためにヒトが造ったモノである、という点に主たる関心があります。

神奈川県川崎市出身。大学では看護を、大学院では健康社会学を学びました。今は健康生成論の立場で何が健康をつくるのか、すなわち健康要因の探求と、病いや障害とともに生きる人々の生活・人生と支援のあり方について研究をしています。

主な研究テーマとしては、初等中等教育における ICT 活用やメディア教育、情報教育に関心をもっています。

佐賀県出身。これまで思春期・青年期の人が集まるフリースクールにおける生活臨床や、大学における相談活動である学生相談を行ってきました。人を支援するということは、支援する相手が変わっていくだけではなく、カウンセラー自身もまた変容していくプロセスであると思います。カウンセラーの成長プロセスや、スーパービジョンなどのカウンセラーの成長支援に関心があります。

ソフトウェア技術者として企業に勤めた後、オブジェクト指向開発手法に関する開発支援を行うために独立し、学位取得を期に、活動の場を大学に移しました。「楽しくなければ!」をモットーに、ソフトウェア開発プロセスと技術の改善、開発に力を注いでいます。

都市銀行勤務、大阪教育大学助教授等を経て現職。生活の安全・安心に資することを目標に、現代社会におけるリスクと生活について研究しています。

様々な生命現象において、遺伝子やタンパク質といった小さな構造がどのような役割を担っているかを、それらが持つ情報(DNA塩基配列やアミノ酸配列)から明らかにする研究を行っています。現在は、共生や進化といった現象に興味があります。

東京都出身。音響・映像等のメディア情報が人間に及ぼす影響を脳科学・情報環境学等の手法を活用して多角的に捉え、「脳にやさしいメディア」を実現するための研究をしています。可聴域をこえる超高周波の基幹脳活性化効果の応用にも取り組んでいます。
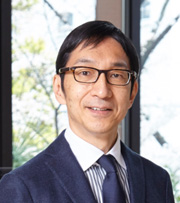
フランス近・現代文学の研究・翻訳を主軸に、フランスや日本の文学テキストの分析を専門領域としてきました。映画論や、文芸作品のアダプテーションに関する研究も学際的な視点に立って行っています。

新潟県出身。原子・分子やその集合の示す多様な形、反応、機能を司る原理を研究しています。結果を、材料、環境、医療など社会に還元できることは、化学の魅力、醍醐味だと思います。自身は理論と計算を研究道具としますが、国内外の実験家と協力しています。

高等教育の制度・組織・政策・内容などについて、主に歴史社会学的なアプローチによって研究してきました。専門職養成、学問領域・内容の制度化、学位・資格・教育プログラム、高等教育の政策過程など、テーマや分析対象は多種多様ですが、特にわが国の高等教育における諸事象を、明治以降の大きな流れの中で位置づけ問い直す作業が重要だと考えています。

総合病院の臨床心理士を経て大学教員となり、その後も精神科クリニックやカウンセリング専門機関で臨床活動を行ってきました。C. G. Jungの分析心理学やロールシャッハ法を基盤にして、想像活動、パーソナリティ、精神病理などを研究しています。

専門は情報工学,教育工学です。私たちの生活様式を変えつつあるコンピュータやネットワークの技術を活用した,学習者に適した学習環境の実現に興味があります。データに基づいた教材や学習システムの構築,改善のためのしくみ作りを進めています。

地域にある教育相談室にて児童心理臨床に携わってきました。その実践の中で地域社会に出向いた援助活動も行うようになりました。大学教員となり心理職養成に関わる立場になった現在も、個人心理臨床や援助者へのコンサルテーション活動などを続けています。

専門は経営学、人的資源管理です。現在、就労者の大半は雇われて働いているので研究意義は高いと思います。多様な人材の雇用管理(人材の採用、育成、報酬等)に関心があり、非正規労働者、女性、国際化(雇用に関する世界的潮流)等について探求しています。

認知心理学をバックボーンとし、学習・教育を効果・効率・魅力的に設計・改善するための方法論の確立と実践、学問領域名で言うならば「インストラクショナル・デザイン(ID)」を主な専門としています。「学習をするのは学習者である」という立場で、教員が教えるのではなく学習者自身に学ばせるための設計とはどういうものかを検討し、設計したり実践したりをしています。

青春の旅の途中で、英国で社会人類学と出会いました。個性的な学者たち、大志を胸に世界中から集まった学生たち、そして国を追われた人々の現実・・、性別、肌の色、年齢、障害のあるなし関わらず、人間の生きることの切実さと社会というものの奥深さに圧倒され、胸が震えました。あの頃の気持ちを、これからも持ち続けて行きたいと思います。

情報デザイン、空間デザイン、ビジュアルデザインの分野で研究・教育活動を行ってきました。携帯情報端末を使用した鑑賞支援等、視覚伝達を主に、人と情報をつなぐデザインの研究を行っています。

専門は、西洋美術史です。特に18世紀フランス美術を研究しています。芸術作品をまず見ることから出発して、「何が」、「どのように」芸術作品に表現されているのか、つまり図像学・図像解釈学、そして様式分析による作品研究、それから、当時の人々がどのように作品を見たり購入したり蒐集したりしていたのか、批評家、鑑賞者、所蔵者の趣味の解明を目指す受容史研究をはじめ、複数のアプローチから研究を行っています。近年は、風景画に関心を持っています。

専門は、世界の食料需給及び食料需給モデルを用いた将来見通し、農産物等の国際コモディティ市場、農業経済学に関わる研究です。農林水産政策研究所の上席主任研究官や経済協力開発機構(OECD)本部の農業政策アナリストなどを経て現職に着任。世界の穀物等を含めた食料の動向が注目されていますが、フランス、インドネシア、タイ、米国など海外経験を踏まえて、多様な視点でこれらの世界的潮流を捉えていきたい。

1994年に堀部安嗣建築設計事務所を設立。住宅を中心に質の高い建築のあり方を探って設計活動を行っています。自然、人体、信仰、経済など建築を取り巻く様々な事柄を学び、その学びの実践を通して、より実感を伴って環境と向き合う大切さを伝えたいと思います。

横浜国立大学経営学部卒業、一橋大学大学院商学研究科修士課程修了・博士後期課程単位修得退学、一橋大学助手、文教大学専任講師、横浜国立大学助教授・教授・名誉教授、2018年から放送大学教授。オペレーションズ・マネジメント&ストラテジー学会会長等を歴任。

神戸市生まれ、東京大学工学部都市工学科卒業、経済学研究科博士課程単位取得退学。指導教員は西部邁先生でしたが大学構内で指導を受けたことはほとんどありませんでした。同大教養学部・総合文化研究科教授、柔道部長を経て2018年に放送大学に着任。生涯武道家です。現在は「共有資本」について執筆しています。

これまでは教育領域で心理臨床を行ってきました。家庭や職場そして学校という場は日々変化し、そこで生活する私たちも変化します。そこでの心理臨床は変化に向けた徴候を察知し、場の変化に乗じた支援が必要になります。そのような変化の中で自分を知るという学びを得られることが成長を促進するようです。最近のテーマは、学ぶということや知るということを心理臨床の視点から考え直すことです。

上古音と呼ばれる中国・先秦時代の音韻体系を、考古学的発掘によって得られた出土文字資料を用いて研究しています。外国語を学ぶことで、その担い手たちへの理解を深めると共に、自らの母語を省みるきっかけとしてください。

20 世紀アメリカ小説研究を出発点として、映画・写真・建築・音楽などを含む、学際的なアメリカ文化研究を行っています。合衆国以外の地域の人々にとっての「アメリカ」を解明することも現在の研究テーマのひとつです。

三重県出身。大学は英文学科でしたが、社会人経験を経て、大学院から心理学を学び始めました。発達のプロセスには、文化を超えた普遍性がある一方で、文化によって行動や認識、表現等に違いも見られます。文化と発達の関わりに関心をもって、研究しています。

児童福祉施設(児童心理治療施設)に勤務後、東京都立大学で学生相談を担当してきました。大学院修了後の30数年はずっと臨床の現場にいて、クライエントのニーズに合った支援を模索してきました。

岐阜県出身。人が日々の生活の中で行う様々な社会的判断の背後にある認知的なメカニズムを研究しています。自身が新しいモノ好きということもあって、新たな科学技術が人間の心や行動に与える影響にも関心を持っています。

徳島県出身。専門は教育工学です。学習情報検索システムやeラーニングシステムなど、広くICTを活用した学習支援システムに関する研究開発に取り組んでいます。

画像や映像、音声、テキストといった多様な情報の処理や、それらを統合したデータ分析、データベース化手法などについて研究を行っています。特に、画像データベース、映像検索、大規模データの処理・分析など。

神奈川県出身。所謂文系科目が得意でしたが,理系的な理解の仕方に魅力を感じて大学では理系学部に進学。物質が示す機能の理論研究をしていますが「完璧に分かり尽くした」と思える瞬間は大満足で,適性に負けて好奇心に逆らわずによかったなと思っています。

医療看護実践場面における状況把握と臨床における推論、すなわちアセスメントを中心に研究を進めています。さらにそれらの成果を広く還元できるような教育研修体制の構築や整備に尽力したいと考えています。

東京都出身。近代イギリス政治思想史の研究を、現代政治理論、特に自由主義の政治理論の研究と融合させるかたちで追究しています。政治という実践的な現象を、理論的に把握することの意義を、皆さんといっしょに考えていきたいと思います。

情報と人間/教育との関わりを広く研究しています。学習・学術コンテンツの開発・共有・流通・電子出版(特にオープン教育資源)、サイバーボランティア(eボランティア)、国際技術標準とデジタルエコシステム、学習解析と電子履歴証明に関心があります。

私は仕事をしながら博士課程に進学し博士号を取得しました。仕事と両立させながら大学で学ぶことの大変さはよく知っています。忍耐強く強靭な精神力で乗り切ってください。学問とのすばらしい出会いを大切に。

出身地は上海です。1988年留学のため来日しました。長年にわたる企業法務等に関する実務経験があります。働きながら慶應義塾大学博士号(法学)を取得しました。専門分野は、商法です。主に理論と実務との融合を図る視点に立って保険法を研究しています。





