Vol.17 日本語とコミュニケーション
滝浦真人教授(人間と文化コース・人文学プログラム)
2015年8月26日
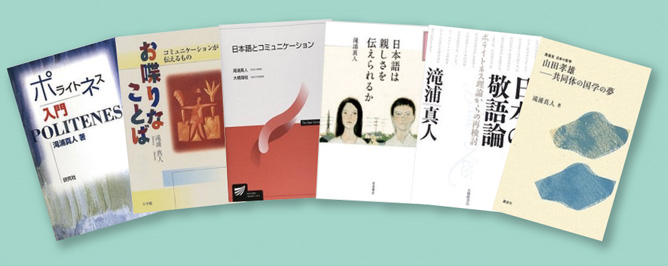
私は「言語学科」の出身です。大学院生時代は「失語症」を対象として、脳の損傷で言語の運用がどう壊されるか?を研究していましたが、しばらくして関心がちょうど反転する具合となり、何が人と人のコミュニケーションを成り立たせているか?を探りたくなりました。それ以来、言語が持つ対人的な機能を中心に研究しています。
「ポライトネス」という言葉は初耳かもしれません。「言語的対人配慮」といった意味ですが、日本語で配慮というと敬語のような丁重さの方だけに意識が行きがちです。でも「ポライトネス」の考え方は、人を"敬して避ける"遠慮も、"仲間として近づく"共感も、等しく意味のある対人配慮だと捉えます。日本語の「標準語」は、百年ほど前に人為的に定められ、「作法」のように学校で教えられ、おかげで日本全国に定着しました。しかし「作法」の力を頼ったツケとして、かしこまった敬語は発達しても、上手に親しさを伝える言葉は発達しませんでした。社会が大きく変わった現在、日本語のポライトネスにも変化の兆しが見えています。
今年度開設科目で大橋先生と共同で制作した「日本語とコミュニケーション」には、こうした自分の研究から得られた観点がたくさん含まれています。これから日本語がコミュニケーション上手な言語になるには何が必要かも考えようとしています。日本語とコミュニケーションに関心のある皆さんぜひ見てください!




