放送大学叢書
放送大学叢書最新刊
「新しい観光学」刊行のお知らせ
放送大学叢書は、放送授業で使用した印刷教材をもとに、豊かな教養の書として改めて刊行したものです。
以下の放送大学叢書が発売され、全国の書店やアマゾンなどのインターネット書店で購入できます。
また、出版社の左右社から直接ご購入いただくこともできます。
本学在学生が出版社から直接購入する場合、定価(税込価格)の1割引となるうえ送料無料でお届けしますので、出版社の左右社へお問い合わせください。
最新刊
新しい観光学
十代田 朗 著
放送大学叢書 062
ISBN 978-4-86528-443-0
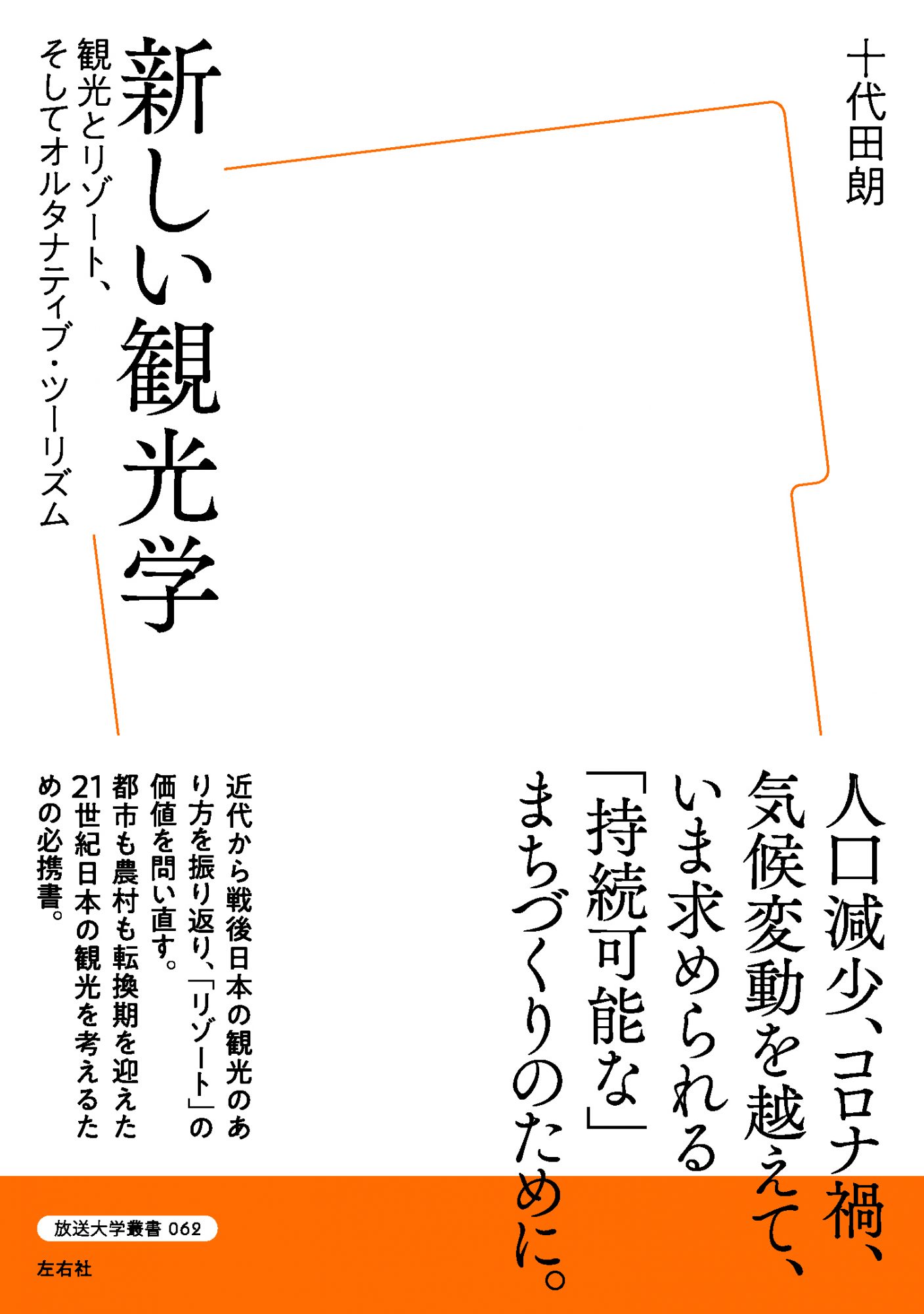
いまなぜ、国家政策、地域の振興策、さらにはまちづくりまで、さまざまなレベルで「観光」に注目が集まっているのだろうか
少子高齢化に消滅自治体、東日本大震災やコロナ禍に象徴される自然災害の数々。
大きく変わりつつあるわが国の姿を背景に、いま、観光そのものも多様化し、変容しつつあると言われて久しい。
転換点にある観光の姿を「観光」「リゾート」「オルタナティブ・ツーリズム」の視点から見直したとき、
都市にできること、農山魚村にできること、それぞれの地域のめざすべきあり方が見えてくる──。
オーバーツーリズム問題やIRの可能性、グリーンツーリズム、ワーケーションやブリージャーなど、
近年の大きな話題を深く理解するために、基礎知識編、歴史編、展開編に加えて、今後の課題と方向性を提示。
多数の図表や事例を用いて具体的に語り、主要出来事年表も備えた、これからの観光に携わるすべてのひとのための教科書。
十代田 朗 (ソシロダ・アキラ)
國學院大學観光まちづくり学部教授。社会工学、都市・地域・国土計画、観光計画、観光地・リゾート発展史学、観光まちづくり論。博士(工学)。
1961年東京都生まれ、神奈川県育ち。東京工業大学工学部社会工学科卒業、同大学院社会工学専攻修士課程修了。株式会社三菱総合研究所、東京工業大学社会工学科、新潟大学工学部建設学科、東京工業大学大学院情報環境学専攻、同大学環境・社会理工学院建築学系を経て、現職。その間、立教大学観光学部兼任講師、Universität Innsbruck, School of Management, Visiting Professor、放送大学客員准教授を歴任。
主要著編書・訳書
『日本別荘史ノート』(共著、1991年)、“Change Management in Tourism - From 'Old' to 'New’ Tourism”(共著、2008年)、『観光まちづくりのマーケティング』(編著、2010年)、『観光の新しい潮流と地域』(編著、2011年)、『近代別荘建築』(監修、2022年)、『観光まちづくりの展望』(共著、2024年)等がある。
[目次]
はじめに
基礎知識編
第一章 今なぜ観光か?
第二章 観光の概念の拡がり
歴史編
第三章 近世以前の観光日本史
第四章 近代の観光日本史
第五章 戦後の観光日本史
展開編
第六章 都市でのオルタナティブ・ツーリズムの展開
第七章 農山漁村でのオルタナティブ・ツーリズムの展開
今後の課題と方向性編
第八章 持続可能な観光振興に向けての課題と方向性
年表/参考文献
おわりに
既刊
61.「文学のエコロジー」
宮下 志朗 著
放送大学叢書 061
ISBN 978-4-86528-385-3

古今東西、文学を取り巻く環境はかように変化してきた
東京大学名誉教授による文学講義全12章
口誦文学と写本、パトロン文化、出版と検閲、著作権、文学賞、読書習慣と識字率、印税、電子書籍──
多彩な切り口から文学を取り巻く環境の変化を解説する。
◉世界の名作古典、名だたる作家たちのエピソードが多数登場
出版契約におけるフロベールと編集者の金銭交渉
借金まみれから再起したバルザックのメディア戦記
モダニズム作家を支えたパリの書店店主の女性たち
著作権をめぐる「三島由紀夫手紙事件」
宮下 志朗 (ミヤシタ・シロウ)
1947年生まれ。東京大学・放送大学名誉教授。フランス文学、書物の文化史。単著に大佛次郎賞を受賞した『本の都市リヨン』(晶文社)、『読書の首都パリ』(みすず書房)、『ラブレー周遊記』(東大出版会)、『モンテーニュ 人生を旅するための7章』(岩波新書)、『パリ歴史探偵』(講談社学術文庫)など。訳書にラブレー『ガルガンチュアとパンタグリュエル』全5巻(ちくま文庫、読売文学賞・日仏翻訳文学賞)、モンテーニュ『エセー』全7巻(白水社)、『ヴィヨン全詩集』(国書刊行会)、『フランス・ルネサンス文学集』全3巻(共編、白水社)、バルザック『グランド・ブルテーシュ奇譚』(光文社古典新訳文庫)、グルニエ『長い物語のためのいくつかの短いお話』(白水社)など。
60.「これからの学力と学習支援」
市川 伸一 著
放送大学叢書 060
ISBN 978-4-86528-378-5

児童・生徒の「心」のしくみから学習指導を考える、教育改善に必携の書!
個別指導、授業研究の実践に取り組んできた教育心理学の第一人者である著者が打ち出す、これからの教育の方向性。放送大学で話題となった授業を全面改訂して発刊しており、現場での学習指導にかかわる教師必読の一冊になっています。
市川 伸一(イチカワシンイチ)
1953年東京生まれ。東京大学文学部卒業。文学博士。現在,東京大学名誉教授,帝京大学中学校・高等学校校長。中央教育審議会教育課程部会委員として学習指導要領の改訂に関わる。専門は教育心理学。認知心理学を基盤にした個別学習支援や授業づくりなどの実践に携わっている。著書に、『考えることの科学』(中公新書)、『学ぶ意欲の心理学』(PHP新書)、『学力低下論争』(ちくま新書)、『学ぶ意欲とスキルを育てる』(小学館)、『「教えて考えさせる授業」を創る アドバンス編』(図書文化社)など。
59.「[新版]少年非行」
鮎川 潤 著
放送大学叢書 059
ISBN 978-4-86528-332-7
![「[新版]少年非行」表紙イメージ](/about/pr/ouj-series/assets/images/sousyo059.png)
改正少年法から見えてくる私たちの社会のしくみ
センセーショナルに報じられたあの事件の少年は、その後、どのような裁きを受け、処遇に服しているのだろうか。
いま社会はどのように少年に非行に向き合い、処遇しているのか。一貫して減少し続けている発生件数、日本が誇る信頼の原理による保護観察・更生保護、そして処罰的処遇へと傾く法改正。少年非行をめぐって、社会の処遇を中心にその全体像を描くロングセラーを、2021年改正少年法を踏まえて全面改訂しました。
鮎川 潤(アユカワ・ジュン)
関西学院大学名誉教授。少年非行、犯罪学、刑事政策、逸脱行動、社会問題研究。博士(人間科学)。保護司、更生保護施設評議員、学校法人評議員、少年院視察委員会委員。1952年愛知県生まれ、東京大学文学部第四類(心理学・社会学)卒業、大阪大学大学院人間科学研究科後期博士課程中途退学。松山商科大学(現・松山大学)人文学部社会学科専任講師、金城学院大学文学部社会学科・現代文化学部福祉社会学科教授、関西学院大学法学部教授、スウェーデン国立犯罪防止委員会客員研究員、南イリノイ大学カーボンデール校フルブライト研究員、ケンブリッジ大学、ウィーン大学、デラウェア大学客員研究員、中国・吉林大学、蘇州大学、中国人民大学への派遣教授、法務省法務総合研究所研究評価検討委員会委員、地方自治体選挙管理委員会委員、法務省矯正研修所支所、家庭裁判所調査官研修所の講師などを務めた。
58.「人間発達論」
住田 正樹 著
放送大学叢書 058
ISBN 978-4-86528-057-9

親子関係のなかに自我を育む幼少期、学校や先生、仲間と出会う子ども時代、職業や配偶者の選択など決断を重ねながら自分らしい人生を重ねてゆく青年時代、そしてさまざまな道のりで老いてゆく老年期。 社会をつくり、社会のなかで変わり続けながら生きていく私たちのすがたを最新の調査分析でみる。
住田 正樹(すみだ・まさき)
博士(教育学)。1944年兵庫県生まれ。教育社会学、発達社会学。放送大学名誉教授、九州大学名誉教授。主な著書に『子どもの仲間集団と地域社会』『子どもの仲間集団の研究』『地域社会と教育』『子ども社会学の現在』、編著や訳書に『子どもたちの「居場所」と対人的世界の現在』(共編著)『教育社会学』(共編訳)『リトルリーグの社会学』(監訳)『ピア・パワー』(監訳)『子どもへの現代的視点』(共編著)『子どもと家族』(編著)『子どもと地域社会』(編著)『子どもの発達社会学』(共編著)『家庭教育論』(編著)『変動社会と子どもの発達』(共編著)などがある。
57.「建築を愛する人の十三章」
香山 壽夫 著
放送大学叢書 057
ISBN 978-4-86528-043-2

家族を支える「大黒柱」、目は心の「窓」、
私たちを守り、ひとつに包む「壁」、「門」は招き誘い、また拒む──。
私たちが住み、ともに暮らす空間=建築とはなんだろうか。
劇場や学校、公共施設を中心に第一線で活躍し続ける建築家・香山壽夫が、
建築を愛するすべての人にわかりやすく語りかける建築の真髄。
新たな章を増補した新装版。
香山 壽夫(こうやま・ひさお)
建築家。1937年、東京都生まれ。東京大学名誉教授、香山建築研究所会長、アメリカ建築家協会名誉会員。主な受賞に日本建築協会作品賞、村野藤吾建築賞、日本減築学会大賞、アメリカ劇場協会賞、日本芸術院賞など。主な作品に、彩の国さいたま芸術劇場、東京大学工学部一号館改修、聖学院大学礼拝堂、函館トラピスチヌ・旅人の聖堂、東京大学伊藤国際学術研究センター、ロームシアター京都などがある。
56.「パレスチナ問題の展開」
高橋 和夫 著
放送大学叢書 056
ISBN 978-4-86528-007-4

パレスチナ問題とはなにか。 国際政治のダイナミズムのなかでの中東情勢の変化がわかる。 宗教、民族、石油をめぐる利害の交差による紛争と難民問題はいかにして起こったか。 ISやシリア内戦とはどう関係するのか。 また、ジョー・バイデン大統領就任までのアメリカの中東政策と バーニー・サンダースにみるようなパレスチナ問題への新しい波とはどのようなものか。 アメリカの中東政策も詳しく見ていく。〈年表パレスチナ問題の歴史付〉
高橋 和夫(たかはし・かずお)
放送大学名誉教授。福岡県北九州市生まれ、大阪外国語大学外国語学部ペルシア語科卒、コロンビア大学国際関係論修士、クウェート大学客員研究員、放送大学教員などを経て2018年4月より一般社団法人先端技術安全保障研究所会長。主な著書に『アラブとイスラエル』(講談社1992年)『イスラム国の野望』(幻冬舎、2015年)『世界の中の日本』(放送大学教育振興会、2015年)『中東から世界が崩れる』(NHK出版、2016年)『現代の国際政治』(放送大学教育振興会、2018年)『国際理解のために(改訂版)』(放送大学教育振興会、2019年)『中東の政治』(放送大学教育振興会、2020年3月)『最終決戦トランプVS民主主義―アメリカ大統領選挙撤退後も鍵を握るサンダース』(ワニブックス、2020年7月)など。
55.「増補 自己を見つめる」
渡邊 二郎 著
放送大学叢書 055
ISBN 978-4-86528-025-8

ニーチェやハイデッガーらのことばをまじえ、崩れ落ちそうになる気持ちを支え引き締めてくれる静かなロングセラー。多くの熱心な聴講生を集めた伝説の講義から生まれた名著に、著者が愛読してやまなかったふたりの哲学者への追悼を込めた2篇を増補した新装版。
渡邊 二郎(わたなべ・じろう)
哲学者。放送大学名誉教授、東京大学名誉教授。専攻は西洋近現代哲学。著書に『ハイデッガーの実存思想』『ハイデッガーの存在思想』(以上勁草書房)、『ニヒリズム』(東京大学出版会)、『構造と解釈』『英米哲学入門』『芸術の哲学』『はじめて学ぶ哲学』『現代人のための哲学』(以上ちくま学芸文庫)、『歴史の哲学』(講談社学術文庫)、『人生の哲学』(角川ソフィア文庫)などがあり、『渡邊二郎著作集』全12巻(筑摩書房)に集成されている。
54.「精神疾患とは何だろうか」
石丸 昌彦 著
放送大学叢書 054
ISBN 978-4-86528-018-0

うつ病患者100万人を筆頭に、いま、精神疾患による患者数は400万人を超えている。 病状や対処法の情報が溢れている一方で、私たちはどこまで〈心の病〉のことを知っているのだろうか。 うつ病患者はなぜこんなにも増えたのか、統合失調症は治すことができるのか、依存症を断ち切る薬はないのだろうか。 現代精神医学の最新の知見を、臨床経験を踏まえた症例とともにわかりやすく説く一冊
石丸 昌彦(いしまる・まさひこ)
1957年愛媛県出身。精神科医。東京大学法学部卒業後、東京医科歯科大学医学部卒業。東京医科歯科大学難治疾患研究所講師、桜美林大学助教授、教授を経て、放送大学教授。主な著書に『統合失調症とそのケア』(キリスト新聞社)、共訳書にフィリップ・G・ジャニカク『根拠にもとづく精神科薬物療法』(メディカル・サイエンス・インターナショナル)などがある。
53.「遊環構造デザイン」
仙田 満 著
放送大学叢書 053
ISBN 978-4-86528-287-0

わたしたちの未来を担うこどもたち。彼らが生き生きと成長し、困難を乗り越えられる人になるために、建築にはできることがある。幼稚園や学校、博物館や科学館、スタジアム、そして町にまで応用され成果をあげている「遊環構造デザイン」の理論と実践をさまざまな事例とともに語る、環境デザインの第一人者による決定版。
せんだ・みつる=建築家、菊竹清訓建築設計事務所を経て、1968年環境デザイン研究所創設。工学博士。日本建築学会会長、日本建築家協会会長、日本学術会議会員、放送大学教授等を歴任。現在、東京工業大学名誉教授、こども環境学会代表理事。 設計作品として、愛知県児童総合センター(日本建築学会賞作品賞)、国際教養大学中嶋記念図書館(村野藤吾賞)、広島市民球場(日本建築家協会賞)等。著書に『子どもとあそび』(岩波新書)、『人が集まる建築』(講談社)、『こどもを育む環境 蝕む環境』(朝日新聞出版社)等がある。
52.「饗映する日本文学史」
島内 裕子 著
放送大学叢書 052
ISBN 978-4-86528-296-2

『古今和歌集』から夏目漱石まで、つながりを知れば文学はもっと楽しい!古典から近代に至るまで、ひとつの文学作品はまた別の作家を産み、作家たちはまた新たな作品を作り続けてきた。「響映」=「響き合い、映じ合う」という視点から史実をひもとく、まるで物語のように読み進められる、ドラマティックな文学史入門。
しまうち・ゆうこ=放送大学教授、国文学。『徒然草の変貌』(ぺりかん社)、『兼好 露もわが身も置きどころなし』(ミネルヴァ書房)、『徒然草文化圏の生成と展開』(笠間書院)、『徒然草をどう読むか』(左右社)、『方丈記と住まいの文学』(左右社)、『批評文学としての「枕草子」「徒然草」』(NHK出版)、『校訂・訳 徒然草』(ちくま学芸文庫)、『校訂・訳 枕草子』(上・下、ちくま学芸文庫)などの著書がある。
51.「衝突と共存の地中海世界」
本村 凌二 ・ 高山 博 著
放送大学叢書 051
ISBN 978-4-86528-284-9

揺れるEU、極端に触れるアメリカ。グローバル化を背景に、近代国民国家の終焉が指摘されるいま、さまざまな文明・民族・宗教が生き続けた地中海世界こそ、目を向ける意味がある。紀元3000年紀、灌漑農業の発達とともに発達したメソポタミア文明、エジプト文明以来、ヨーロッパ・アジア・アフリカを結びつけてきた地中海。そこにはハンムラビ法典とシュメール文字を持ったバビロニア王国、巨大なピラミッドを築いたエジプト、その狭間で群立した小都市国家以来の14世紀までの諸勢力、諸民族の接触と交流と対立をわかりやすく描く
もとむら・りょうじ(1〜8章)=東京大学名誉教授、西洋古代史。『薄闇のローマ世界』でサントリー学芸賞、『馬の世界史』でJRA賞馬事文化賞、一連の業績にて地中海学会賞を受賞。著作に『多神教と一神教』『愛欲のローマ史』『はじめて読む人のローマ史1200年』『ローマ帝国 人物列伝』『競馬の世界史』『教養としての「世界史」の読み方』『英語で読む高校世界史』『裕次郎』『教養としての「ローマ史」の読み方』など多数。
たかやま・ひろし(8〜15章)=東京大学大学院人文社会系研究科教授、西洋中世史。著書に『中世地中海世界とシチリア王国』(R. Lopez Memorial Prize受賞)『神秘の中世王国』『ハード・アカデミズムの時代』『中世シチリア王国』『歴史学未来へのまなざし』『「知」とグローバル化』『ヨーロッパとイスラーム世界』『中世シチリア王国の研究』『Sicily and the Mediterranean in the Middle Ages』などがある。紫綬褒章、サントリー学芸賞、地中海学会賞、マルコ・ポーロ賞受賞。
50.「新・住宅論」
難波 和彦 著
放送大学叢書 050
ISBN 978-4-86528-284-9

物理的にも精神的にも持続可能なデザイン(=サステイナブルデザイン)から住宅の問題を総合的に考えることは可能だろうか。「箱の家」で知られる建築家・難波和彦が日本の住宅の問題を、歴史的、技術的な視点から立体的に捉える。仮設住宅から超高層ビル群まで、3・11の震災以降新たな調査と取材を重ねて生まれたあたらしい住宅論。
なんば・かずひこ=建築家、難波和彦+界工作舎代表。放送大学名誉教授、東京大学名誉教授。代表作に「箱の家」シリーズ(1995年~)がある。主な著書に『戦後モダニズム建築の極北 池辺陽試論』(彰国社)、『箱の構築』(TOTO出版)、『箱の家 エコハウスをめざして』(NTT出版)、『進化する箱 箱の家の20年』(TOTO出版)などがある。
49.「となりの心理学」
星 薫 著
放送大学叢書 049
ISBN 978-4-86528-282-5

人間が「未熟」なまま生まれてくるのはなぜか? ヘビやクモにゾッとするのはなぜか? 日常の出来事、当たり前に思っていることの中から人間の心の不思議に迫ってゆく心理学入門にぴったりの1冊。
ほし・かおる=心理学。放送大学准教授を経て、現在同大学客員准教授。主な著書に『物忘れの心理学』(近代文芸社新書)、『成人発達心理学』(編著、放送大学教育振興会)、『危機の心理学』(共著、放送大学教育振興会)、『発達科学の先人たち』(共編著、放送大学教育振興会)、『心理学概論』(共著、放送大学教育振興会)などがある。
48.「現代中国 都市と農村の70年」
浜口 允子 著
放送大学叢書 048
ISBN 978-4-86528-248-1
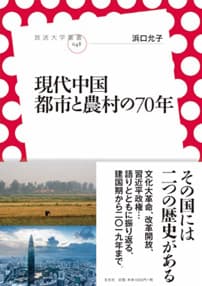
超えがたい格差があるといわれる中国と都市と農村。現代中国を特徴づけるこの二元的社会に注目し、格差の実際と政策的な背景、そこで生きた人々の語りとともに描き出す建国以来の歴史。
はまぐち・のぶこ=放送大学名誉教授。専攻は東洋史学、中国近現代史。主な著書に『北京三里屯第三小学校』(岩波新書)、『中国・近代への歩み』、『中国の近代と現代』(編著)、『東アジアの中の中国史』(共著、以上、放送大学教育振興会)、『村から中国を読む−華北農村五十年史』(共著、青木書店)、『天津史−再生する都市のトポロジー』(共著、東方書店)、調査記録『中国農村変革と家族・村落・国家』、同第二巻(共著、汲古書院)など。
47.「日本社会の変動と教育政策 新学力・子どもの貧困・働き方改革」
小川 正人 著
放送大学叢書 047
ISBN 978-4-86528-241-2

バブル崩壊による日本経済の低迷、雇用の不安定化、格差の拡大、長時間労働など日本社会が変動するいま、教育行政で何が問題とされ、何が優先されているのか。「教育の構造改革」を丁寧に読み解いていく。
おがわ・まさひと=放送大学教授、東京大学名誉教授、教育学博士。主な著書に『教育改革のゆくえ』(ちくま新書)、『市町村の教育改革が学校を変える』(岩波書店)、『現代の教育改革と教育行政』(放送大学教育振興会)、『戦後日本教育財政制度の研究』(九州大学出版会)など。
46.「私教育再生 すべての大人にできること」
安彦 忠彦 著
放送大学叢書 046
ISBN 978-4-86528-222-1

部活動、いじめ、受験勉強。そのどこまでが学校の責任なのだろうか。日大アメフト部問題や教員の加重労働問題などの時事的なトピックスも取り上げながら、家庭・塾・地域に光をあてて考える、教育バランス改革論。
あびこ・ただひこ=名古屋大学名誉教授。専門はカリキュラム学・教育課程論を中心に、教育方法、教育評価。著書に『よくわかる教育学原論』(共編著、ミネルヴァ書房)、『「コンピテンシー・ベース」を超える授業づくり』 (図書文化社)、『最新教育原理』(編著、勁草書房)、『「教育」の常識・非常識─公教育と私教育をめぐって』(学文社)、『新版カリキュラム研究入門』(編著、勁草書房)など。
45.「地域教育再生プロジェクト」
岡崎 友典 著
放送大学叢書 045
ISBN 978-4-86528-204-7

核家族化、少子高齢化、過疎過密化により地域社会は失われてきた。教育を武器に地域社会を再生することはできるだろうか? 明治時代以来の家庭と学校、地域社会の変化を辿り、18の教育実践を検討する。
おかざき・とものり=放送大学客員教員。教育学修士(東京大学)。日本教育社会学会・日本子ども社会学会元理事。主な著書に『家庭・学校と地域社会』(放送大学教育振興会)、『教師が読む子どものための「学校五日制」』(共編著、ぎょうせい)、『ハンドブック事例で読む「学校と家庭・地域」』(共編著、教育出版)などがある。
44.「近現代日本の生活経験」
中川 清 著
放送大学叢書 044
ISBN 978-4-86528-194-1

少子長命化、格差社会、ワーキングプア......。 いま私たちが抱える問題はすべて、150年間の近代化のあゆみの帰結である。 より豊かでより良い生活を求めてきた私たちがどのように「生き方」を変化させてきたか、貧困問題や人工妊娠中絶など、広い視点で今日の問題の本質を捉える。
なかがわ・きよし=生活構造論、社会政策学。同志社大学名誉教授。主な著書に『日本の都市下層』(勁草書房、労働関係図書優秀賞受賞)、『明治東京下層生活誌』(編著、岩波文庫)、『日本都市の生活変動』(勁草書房、生活経済学会賞、社会政策学会学術賞受賞)など。
43.「21世紀の女性と仕事」
大沢 真知子 著
放送大学叢書 043
ISBN 978-4-86528-195-8
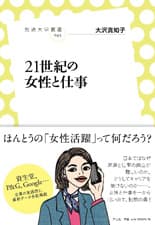
日本ではなぜ家庭と仕事の両立が難しいのか、どうしてキャリアを築けないのか......。女性キャリア研究の第一人者が、日本の女性と仕事にまつわる数々の「なぜ?」を一から問い直す。日本の労働構造、法制度、教育、ジェンダー、企業の対応まで、この一冊ですべてがわかる「女性と仕事」入門書の決定版! Google、P&G、資生堂など先進企業の実践例や、最新データも多数掲載。
おおさわ・まちこ=労働経済学者。社会と個人のあり方の変化や、家族が経済変化によってどのように変わっていくのかを国際比較によって実証研究している。日本女子大学人間社会学部教授。同大学現代女性キャリア研究所所長。コロンビア大学社会科学センター研究員、シカゴ大学ヒューレット・フェロー、ミシガン大学ディアボーン校助教授なども勤めた。著書に『経済変化と女子労働』『女性はなぜ活躍できないのか』など。
42.「道徳教育の方法 理論と実践」
林 泰成 著
放送大学叢書 042
ISBN 978-4-86528-192-7

2018年4月小学校、2019年4月中学校で道徳の教科化がスタート。教科化された「考える道徳の授業」とは。どう変わる?どう作る?《現職教員、教育実習生、保護者必読》
はやし・やすなり=道徳教育論、教育哲学。上越教育大学副学長・教授。文学修士。日本道徳教育方法学会副会長、日本道徳教育学会理事。日本道徳性発達実践学会常任理事。主な著書:『ケアする心を育む道徳教育』(編著)北大路書房、『人間としての在り方生き方をどう教えるか』(共著)教育出版、『モラルスキルトレーニングスタートブック』明治図書、『特別の教科 道徳の授業づくり』(監修)明治図書、『教員養成を哲学する』(共編著)東信堂など。
41.「古代ギリシアにおける哲学的知性の目覚め」
佐藤 康邦 著
放送大学叢書 041
ISBN 978-4-86528-189-7

ヘーゲルもニーチェも、ここからはじまった。哲学という営みの根源を豊穣なる古代ギリシア文化に訪ねる比類のない哲学への〈誘い〉
さとう・やすくに=倫理学、哲学。東京大学名誉教授。主な著書に『ヘーゲルと目的論』(昭和堂)、『カント『判断力批判』と現代』(岩波書店、第18回和辻哲郎文化賞受賞)『教養のヘーゲル『法哲学』』など、共訳書にヘーゲル『法の哲学』(岩波書店)などがある。
40.「天川晃最終講義 戦後自治制度の形成」
天川 晃 著
放送大学叢書 040
ISBN 978-4-86528-185-9

戦前から占領期を経て、戦後地方自治制度の完成期までを、大胆なモデル化と緻密な資料の読み込みで展望。戦後自治史の金字塔とも呼ぶべき天川史学の集大成。
あまかわ・あきら=政治学、占領期の政治過程。横浜国立大学名誉教授、放送大学客員教授。主な著書に『占領下の神奈川県政』『占領下の日本』『占領下の議会と官僚』(以上、現代史料出版)、『戦後日本 占領と戦後改革』全6巻(岩波書店、共編著)、シリーズGHQ民政局資料「占領改革」『第8巻 地方自治1』『第9巻 地方自治2』(丸善)ほか多数。
39.「医学の歴史 歩みを担った人びと、そして体制」
多田羅 浩三 著
放送大学叢書 039
ISBN 978-4-86528-184-2

人類の絶えざる病との苦闘と歩みから学ぶことこそが、健康状態の多様性と向き合った時に新しい地平を開く--公衆衛生学研究の第一人者が、ヒポクラテスから北里柴三郎まで医学を生み育てた天才たちと医学の体制を作った人びとの歩みをたどる。
たたら・こうぞう=公衆衛生学、大阪大学名誉教授。主な編著書に『公衆衛生の思想-歴史からの教訓-』(医学書院、1999年)、『健康日本21推進ガイドライン』(編著、ぎょうせい、2001年)、『公衆衛生-その歴史と現状-』(共著瀧澤利行、放送大学教育振興会、2009年)、『健康科学の史的展開』(共著高鳥毛敏雄、放送大学教育振興会、2010年)、『現代公衆衛生の思想的基盤』(日本公衆衛生協会、2011年)などがある。
38.「貨幣・勤労・代理人 経済文明論」
坂井 素思 著
放送大学叢書 038
ISBN 978-4-86528-181-1

文明という視点に立ったとき、19世紀以来の経済の歴史はどのように見えるだろうか。人びとは生産の場を離れていっそう消費にのめり込み、各種産業では巨大な組織(会社)が日々の生活すみずみまでを左右する。そして、あらゆるものを取引するビジネスの肥大化――。産業革命から今日まで、46の名著とともに、人類史的な視野で見つめる。
さかい・もとし=社会経済学、産業社会論、消費社会論。放送大学教授。主な著書に『経済社会論』『家庭の経済』『経済社会の考え方』『社会経済組織論』『社会的協力論』(すべて放送大学教育振興会)などがある。
37.「日本音楽のなぜ? 歌舞伎・能楽・雅楽が楽しくなる」
竹内 道敬 著
放送大学叢書 037
ISBN 978-4-86528-168-2

歌舞伎や芸能を観賞してこのような感想をもったことがありませんか? ・このノリの悪いのは、なんとかならないのか! ・何をいってるのかさっぱり聞きとれなくて眠い! ・どうしていつも語尾を長く震わせているのか? いずれも理由があるのです。日本音楽には日本人が大切にしてきた心が宿っているのです。 近世日本音楽の第一人者が15の疑問に答える類例のない構成。 読めば歌舞伎、能楽がもっと深く、広く、長く、楽しめるようになります!
たけうち・みちたか=日本近世音楽史。武蔵野音楽大学、お茶の水女子大学、東京藝術大学、国立音楽大学などの非常勤講師のほか、文化庁芸術祭音楽部門審査委員、芸術選奨選考委員、芸術作品賞選考委員、文化財保護審議委員などを歴任。一般財団法人古曲会の設立、運営に尽力。主著に『河東節二百五十年』(河東節二百五十年刊行会)、『近世芸能史の研究』(南窓社、東洋音楽学会田邉賞)、『近世邦楽研究ノート』(名著刊行会、日本演劇学会河竹賞)、『日本音楽の基礎概念』(放送大学教育振興会)、『続近世邦楽考』(南窓社)。
36.「社会調査 しくみと考えかた」
原 純輔 著
放送大学叢書 036
ISBN 978-4-86528-165-1

世論調査、選挙予想、マーケティング、福祉調査、アンケート。いま世の中に氾濫する社会調査を正しく理解し、有益なツールとするための基本を学ぼう。大学生からマーケティング担当者、そして調査を受ける私たちまですべての人に役立つ1冊。
はら・じゅんすけ=社会学。東北大学名誉教授。主な著書に『社会階層』(共著、東京大学出版会。英語版、韓国語版も)、『社会調査演習』(共著、東京大学出版会)『流動化と社会格差』(編著、ミネルヴァ書房)などがある。
35.「ヘーゲルを読む 自由に生きるために」
髙山 守 著
放送大学叢書 035
ISBN 978-4-86528-155-2

ヘーゲル哲学は、いまこそ、私たちに必要な哲学だった! カントの二元論を乗り越え、ヘーゲルが追求したのは、私たちが自由に生きる、その哲学的根拠だった。『精神現象学』をはじめ、難解で知られるヘーゲル哲学の全体像を「自由」の哲学として読みなおす。
たかやま・まもる=ドイツ哲学。東京大学名誉教授。主な著書に『ヘーゲル哲学と無の論理』『因果論の超克』『自由論の構築』(ともに東京大学出版会)『ヘーゲル事典』(共編、弘文堂)などがある。
34.「戦前史のダイナミズム」
御厨 貴 著
放送大学叢書 034
ISBN 978-4-86528-154-5

「戦後◯◯年」ばかりが言われる今日、果たして私たちは「戦前」をしっかりわかっているのだろうか? 天皇と宮中、元老、貴衆両院、そして軍部。さまざまなアクターが織りなす「戦前史」を、明治・大正・昭和、3代の天皇を軸に御厨貴が描きだす! 司馬遼太郎や大佛次郎、松本清張らを通じて、いかに歴史を物語るべきかをも論じる名講義。
みくりや・たかし=政治史、オーラル・ヒストリー、公共政策。東京大学名誉教授、放送大学客員教授、青山学院大学特任教授。主な著書に『政策の総合と権力』(東京大学出版会、サントリー学芸賞受賞)、『馬場恒吾の面目』(中央公論新社、吉野作造賞受賞)、『権力の館を歩く』(毎日新聞社)、『日本の近代3 明治国家の完成』(中公文庫)ほか多数。
33.「方丈記と住まいの文学」
島内 裕子 著
放送大学叢書 033
ISBN 978-4-86528-145-3

理想の生き方は住まいとリンクする! 方丈記を源流とし、日本文学における住まい観の多様な広がりを浮き上がらせる、意欲的な一冊。鴨長明、兼好から鷗外、漱石、森茉莉、吉田健一まで...先人たちは、住居と日常に何を見出したか? 『徒然草』に描かれた"好ましくない室内描写"など興味深い資料も収録。
しまうち・ゆうこ=国文学者。専門は『徒然草』を中心とする批評文学。放送大学教授。著書に『徒然草をどう読むか』ほか多数。
32.「哲学の原点 ソクラテス・プラトン・アリストテレスの知恵の愛求としての哲学」
天野 正幸 著
放送大学叢書 032
ISBN 978-4-86528-149-1

哲学とはいかなる営みなのか。ソクラテス・プラトン・アリストテレスに哲学史2400余年の原点を訪ね、思考の筋道が甦るギリシャ哲学入門。
あまの・まさゆき=ギリシャ哲学。東京大学名誉教授。主な著書に『イデアとエピステーメー−プラトン哲学の発展史的研究』『正義と幸福−プラトンの倫理思想』(東京大学出版会)がある。
31.「ミュージックスとの付き合い方 民族音楽学の拡がり」
徳丸 吉彦 著
放送大学叢書 031
ISBN 978-4-86528-143-9

人間はなぜ音楽をつくり演奏しているのか。音楽という営みの全体像に迫る、第一人者による民族音楽学入門。西洋中心主義的な音楽観が180度覆される1冊。索引・文献一覧を完備。
とくまる・よしひこ=音楽学、とくに音楽記号学と民族音楽学を専攻。2002年から2007年まで放送大学教授、現在はお茶の水女子大学名誉教授、聖徳大学教授。著書に『民族音楽学』『民族音楽学理論』(ともに放送大学教育振興会)、『音楽とはなにか』(岩波書店)、『三味線音楽の旋律的様相』(仏文)、『音楽・記号・間テキスト性』(英独仏文)など。共編に『ガーランド世界音楽事典7 東アジア』(英文)などがある。
30.「科学の考え方 論理・作法・技術」
濱田 嘉昭 著
放送大学叢書 030
ISBN 978-4-86528-128-6

繰り返しを見つける、意味のある桁数で計算する、帰納法と演繹法を組み合わせる、誤差の種類を見分ける――。あらゆるジャンルの専門課程に進む前に身につけるべき科学的な発想法、作法、データ分析の技法をわかりやすく解説。科学とは何か、一歩前に進みたい人のための科学概説講義!
はまだ・よしあき=物理化学・分子分光学。薬学博士、放送大学名誉教授。 主な著書に『実験科学とその方法』『基礎化学』『物質循環と人間活動』『量子化学』(以上共編著、放送大学教育振興会)などがある。
29.「心をめぐるパラダイム 人工知能はいかに可能か」
西川 泰夫 著
放送大学叢書 029
ISBN 978-4-86528-126-2

こころとは一体何か? 神聖で不滅の〈魂〉なのか、それとも良く出来た〈コンピュータ〉に過ぎないのか? アリストテレスの昔から、最新の人工知能研究まで、人類の探究の歴史をわかりやすくたどる心理学史物語。幕末から戦後へ、日本の心理学がたどった数奇な運命も1章を設けて解説します。
にしかわ・やすお=心理学史、認知科学。文学博士、上智大学名誉教授・放送大学客員教授。 主な著書に『心とは何か―環境と人間―』『ブラック・ボックス的人間論』(講談社)、『心の科学のフロンティア』(培風館)、『行動医学』(講談社)、『認識のかたち』(誠信書房)などがある。
28.「立憲主義について 成立過程と現代」
佐藤 幸治 著
放送大学叢書 028
ISBN 978-4-86528-113-2

憲法改正問題で毎日のように「立憲主義」の言葉をメディアで見ます。 ところで、立憲主義とはそもそもどんな「主義」なのか。 本書は、ギリシャ以来の知の歴史から立憲主義の意味を語り、憲法九条をはじめとする日本国憲法の精神を探る壮大な試みです。 憲法改正問題でゆれる現在に必要な一冊、佐藤憲法学のもう一つの成果です。
さとう・こうじ=憲法学。京都大学名誉教授。 司法制度改革審議会会長などを務めた。主な著書に『憲法』(青林書院)『憲法訴訟と司法権』(日本評論社)『現代国家と司法権』『日本国憲法と「法の支配」』『憲法とその"物語"性』『現代国家と人権』(いずれも有斐閣)『日本国憲法論』(成文堂)など。
27.「芸術は世界の力である」
青山 昌文 著
放送大学叢書 027
ISBN 978-4-86528-117-0

世界の根源的なパワーを表現しつくした、古典芸術の傑作に深く酔いしれるためにはこうすれば良い! 感動と驚きと未知なる体験が待っている、常識をこえた西洋芸術入門書。 放送大学人気教授による入魂の一冊。カラー口絵16頁。 «ヴィーナスの誕生»のヴィーナスに、女性の肉体美を感じたら不謹慎なのか? いや、そこから芸術体験は始まると本書は語ります。
あおやま・まさふみ=放送大学教授。博士(東京大学)。美学、芸術学、自然哲学。 主な著書に『美学・芸術学研究』『芸術史と芸術理論』、編著書に『舞台芸術への招待』『社会の中の芸術』『比較思想・東西の自然観』(いずれも放送大学教育振興会)などがある。
26.「家族と法 比較家族法への招待」
大村 敦志 著
放送大学叢書 026
ISBN 978-4-86528-116-3

新旧民法の比較、中国や韓国など東アジア諸国との比較、さらに現行法と仮想状態との比較。3つの比較を通じて、日本の家族法の考え方を知り、社会の変化や技術の進展を見据えたありうる家族法のすがたを考える。概説書のサブテキストに最適の1冊!
おおむら・あつし=法学(民法)。 東京大学教授。法制審議会民法(債権関係)部会幹事、生殖補助関連親子法制部会幹事。成均館大学、ソウル国立大学、パリ第2大学、コロンビア・ロースクールなどの客員教授を歴任。主な著書に『法典・教育・民法学』『家族法 第3版』『基本民法Ⅰ~Ⅲ』(以上有斐閣)、『民法総論』『民法改正を考える』(以上岩波書店)、『生活民法入門』(東京大学出版会)などがある。
25.「少年非行 社会はどう処遇しているか」
鮎川 潤 著
放送大学叢書 025
ISBN 978-4-86528-104-0

世間をにぎわせたあの少年。彼らはその後どのように裁かれ、刑に服し、更生への道を歩んでいるのだろうか。補導・送致から審判、保護観察・自立支援まで、少年非行に対するわたしたち社会の処遇の全体像をわかりやすく示す。最新の第4次少年法改正、裁判員制度のもたらす影響などにも言及、学校関係者や保護者にも役に立つ1冊。
あゆかわ・じゅん=刑事政策、犯罪学、逸脱行動・社会問題研究。関西学院大学教授。更生保護施設評議員など歴任。主な著書に『再検証 犯罪被害者とその支援』(昭和堂)、『少年犯罪』(平凡社新書)、『犯罪学入門』(講談社現代新書)、『新版 少年非行の社会学』(世界思想社)などがある。
24.「変化する地球環境 異常気象を理解する」
木村 龍治 著
放送大学叢書 024
ISBN 978-4-903500-74-4

なぜ雨が降り、風が吹くの? 豪雨や台風、豪雪はどうして起きるの? マクロな視野で地球全体の環境を捉え、気象の基本から異常気象まで正しく理解するための基本の1冊。
きむら・りゅうじ=気象学、海洋物理学、地球流体力学。東京大学名誉教授。主な著書に『地球流体力学入門』(東京堂出版)、『改訂版 ながれの科学』(東海大学出版会)、『日本の気候』(共著、岩波書店)など多数。
23.「宇宙像の変遷 古代神話からヒッグス粒子まで」
金子 務 著
放送大学叢書 023
ISBN 978-4-903500-60-7

古代以来、時代ごとの技術的・思想的制約を受けながら、私たちはロゴス(理)でコスモス(宇宙)を説明しようとしてきた。その止むことのない探究が、時計を生み、暦を生み、地図や望遠鏡、そして数学や物理学そのものをうみだしてきたのだ。ヒッグス粒子発見の意味まで、人類の壮大な精神史をえがく科学思想史。
かねこ・つとむ=大阪府立大学名誉教授。科学思想史、科学技術論、情報文化論。主な著書に『アインシュタイン・ショック』(河出書房新社/岩波現代文庫・サントリー学芸賞受賞)、『さらばアリストテレス』(平凡社)、『江戸人物科学史』(中公新書)など多数。
22.「日常生活の探究 ライフスタイルの社会学」
大久保 孝治 著
放送大学叢書 022
ISBN 978-4-903500-92-8

私たちの毎日の生活には、どのような要素があり、共同体や時代の力はどのように働いてきたのだろうか。また急速な高齢化や長期の不況は、どのような変化をもたらしているのだろうか。 「震災」「生涯独身率」「あなた(小坂明子)」「故郷(唱歌)」「ブログ」「ONE PIECE(マンガ)」「村上春樹」など身の回りのさまざまな要素をとりあげ、私たちの日常生活の構造の変化を明らかにし、さらなる「個人化」のすすむ来るべき時代の生活を考える。
おおくぼ・たかじ=ライフストーリー研究。早稲田大学教授。著書に『きみたちの今いる場所』、『日常生活の社会学』『ライフストーリー分析』などがある。
21.「日本人の住まいと住まい方」
平井 聖 著
放送大学叢書 021
ISBN 978-4-903500-10-2

住居という建造物は、ひとびとの生活の数だけ無数にありながら、歴史にきわめて残りにくい。たった数百年前の暮らし方でさえ、明らかにすることは非常に難しい。そんな失われた日本人の暮らし方を、日本建築史の専門家で長くNHK大河ドラマの時代考証にも携っている著者が<ねる><たべる><くつろぐ>など15のキーワードを軸に、多数の図版とともにていねいに解き明かす。日本の隣国、中国・韓国の暮らし方とも比較。わたしたちの生活の今昔が立体的に見えてくる1冊。
ひらい・きよし=建築史学。昭和女子大学特任教授、前学長。東京工業大学名誉教授。元福井県立博物館館長。NHK大河ドラマの建築考証をながく担当している。主な著書に『日本の近世建築』『日本住宅の歴史』『中井家文書の研究』などがある。
20.「学びの心理学 授業をデザインする」
秋田 喜代美 著
放送大学叢書 020
ISBN 978-4-903500-85-0

教師とは子供の成長を幸せに感じ、そのことで自らも成長できる専門家のことである。教育心理学の第一人者、いまもっとも教師に信頼されている秋田喜代美が最新の学問的成果を、授業の実践方法として提示する。何かと教育が批判される困難の中で、教師と生徒が信頼関係を築くにはどのような視点と活動が必要なのか。だれもが共感をもって読める1冊。
あきた・きよみ=教育心理学、学校教育学、保育学。東京大学大学院教育研究科教授。博士(教育学)。主な著書に『読書の発達過程』、『子どもをはぐくむ授業づくり』、『読む心・書く心』、『保育の心もち』などがある。また『教育研究のメソドロジー』、ドナルド・ショーン『専門家の知恵』など編著・訳書多数。
19.「西部邁の経済思想入門」
西部 邁 著
放送大学叢書 019
ISBN 978-4-903500-77-5

経済思想史に名を残す人々は、断じて「単なるエコノミスト」などではなかったーーアダム・スミスからケインズ、シュムペーター、そして新々自由主義、グローパリズムまで。従来の経済学を超えたところから、経済の真の姿を立ち上がらせる経済思想入門の決定版。80年代後半に刊行され今なお光輝を放つ名著に、「新々自由主義」「グローバリズム」「IT革命」を加筆。今日の危機に満ちた資本主義的市場の未来を語るための一冊。
にしべ・すすむ=経済学。東京大学教授などを経て、雑誌「表現者」顧問。評論家。1983年『経済倫理学序説』で吉野作造賞、84年『気まぐれな戯れ』でサントリー学芸賞、92年評論活動により正論大賞、2010年『サンチョ・キホーテの旅』で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。『ソシオ・エコノミクス』『大衆への反逆』『知性の構造』『友情』『ケインズ』など著書多数。
18.「安全で良質な食生活を手に入れる フードシステム入門」
時子山 ひろみ 著
放送大学叢書 018
ISBN 978-4-903500-72-0

戦後、大きく変わった私たちの食生活。その背景には、家族の変化や流通業の変化など、さまざまな社会全体の変化があった。食料生産にのみ着目する従来の食料経済学にかわり、流通から消費者心理まで、全体をとらえる"フードシステム"による、食生活再考。いま私たち消費者が、毎日の食生活の中で出来ることは何か。何を心がければ、安全で良質な食生活を手に入れることができるのか。それを考えるヒントを提供するのが本書の目的である。(「はじめに」より))
とこやま・ひろみ=経済学・フードシステム研究。日本女子大学名誉教授。主な著書に『フードシステムの経済分析』(日本評論社)など。
17.「<こころ>で視る・知る・理解する」
小谷津 孝明 著
放送大学叢書 017
ISBN 978-4-903500-68-3

私たちの"気持ち"はどこから来るのだろうか?『万葉集』や『となりのトトロ』などを例にたどる心理学の基礎理論。フロイト理論や記憶のメカニズム、脳科学が明らかにした知見から、"感情"の仕組み、カウンセリングにおける認知療法まで、わかりやすく概観する。自己実現とは、英語で"self actualization"とか"self realization"という。つまりそれは、自己を現実の行為の中に実現することを意味する。ではどういう自己をどのような行動のうちに実現したらよいのだろうか。それを考えるには、まず私たち自身がどういう存在であるか、また、どういう存在でありうるのかを知らなければならない。(第12章「自己実現のすすめ」より)
こやつ・たかあき=心理学。千歳科学技術大学理事長。主な著書に『認知心理学講座』(東京大学出版会)など。
16.「学校と社会の現代史」
竹内 洋 著
放送大学叢書 016
ISBN 978-4-903500-64-5

高度成長・教育の大衆化時代に、受験戦争やいじめなど幾多の問題の噴出した日本の教育システム。その歴史的変遷をたどり、大衆化して行く姿、英国パブリックスクールを理想像としてきたことの功罪を検討する。戦後日本の教育の移り変わりを見つめ、教育への信頼を取り戻すための1冊。震災後社会の教育は、清水幾太郎のいう若さからくる不思議な新しい力を伸ばしていくものでありたい。そして、「この世界を自分が生まれたときよりも少しでも良いものにしてこの世を去りたい」(J・S・ミル)という高貴な思いを万人がもつような教育でありたい。(「まえがき」より)
たけうち・よう=歴史社会学、教育社会学。京都大学名誉教授、関西大学人間健康学部教授。教育学博士(京都大学)。主な著書に『大学の下流化』(NTT出版)、『社会学の名著30』(ちくま新書)、『学問の下流化』(中央公論新社)など。
15.「西洋近代絵画の見方・学び方」
木村 三郎 著
放送大学叢書 015
ISBN 978-4-903500-63-8

美術史研究の第一人者が教える作品の見方、学び方。西洋近代絵画に描かれたイメージの意味、選択された技法の持つ歴史的背景、さまざまな物語から採用されている主題のニュアンスなど、名画の本質へのアプローチ方法をわかりやすく解説します。レポート作成、論文執筆のための美術史研究ならではの情報整理術も紹介。西洋美術史研究へのはじめの一歩。カラー口絵収録。
きむら・さぶろう=西洋美術史、図像学、アートドキュメンテーション。日本大学芸術学部教授。主な著書に『ニコラ・プッサン』(中央公論美術出版)、『名画を読み解くアトリビュート』(淡交社)など。
14.「老いの心の十二章」
竹中 星郎 著
放送大学叢書 014
ISBN 978-4-903500-48-5

「老年を対象にした心理学や精神医学は、あまりに「認知症」に偏っている。高齢者を認知症の有無で二分するかのごとくである。尺度にしている評価法はすべて減点法である。そこからは老いの豊かさは見えてこない」(「まえがき」より)高齢者の心の「今」を知り、老いをありのままにとらえるための十二章。病院や福祉の現場で高齢者にかかわるひとたちにも「老い」を考えるきっかけになる よう記述。
たけなか・ほしろう=精神科医。元 大正大学教授。主な著書に『高齢者の孤独と豊かさ』『老いの心と臨床』など。
13.「初歩から学ぶ金融の仕組み」
岩田 規久男 著
放送大学叢書 013
ISBN 978-4-903500-46-1

お金を取り巻く仕組みと流れがわかれば、日本経済の出来事が手にとるように分かる!初歩から金融の仕組みがわかるように解説。スワップ、オプション等の基本用語がわかるほか、デフレ対策の経済政策までを説く。
いわた・きくお=学習院大学経済学部教授。金融論、経済政策専攻。主な著書に『金融入門』(岩波新書)、『経済学を学ぶ』(ちくま新書)、『金融危機の経済学』(東洋経済新報社)など。
12.「<科学の発想>をたずねて 自然哲学から現代科学まで」
橋本 毅彦 著
放送大学叢書 012
ISBN 978-4-903500-42-3

ギリシア哲学に起源を持ち、現代、全人類に巨大な影響を及ぼしている<科学の発想>とは何か。お雇い外国人ベルツが述べた「西洋の科学の世界は決して機械ではなく、一つの生命なのである」ということばの真意を歴史にたずね、<科学の精神>の来歴を丁寧にたどる、科学思想史の基本の1冊。
はしもと・たけひこ=東京大学大学院総合文化研究科教授。科学史家。
11.「教育の方法」
佐藤 学 著
放送大学叢書 011
ISBN 978-4-903500-34-8 C0337

いま、社会に求められる学校とはどんな学校なのか。誰もが体験してきたが故に、ともすれば客観的に認識することの難しい授業の時間。そこで起きていることを比較・分析する方法論を示し、授業研究の歴史を概観する。「学びの共同体」を提唱する著者による、学校の未来を考えるための1冊。
さとう・まなぶ=教育学博士。東京大学大学院教育学研究科教授。全米教育アカデミー会員、日本学術会議会員、アメリカ教育学会名誉会員。日本教育学会前会長。
10.「<中国思想>再発見」
溝口 雄三 著
放送大学叢書 010
ISBN 978-4-903500-29-4

中国が成長をつづける秘密はどこにあるのか? これまで日本的な概念で誤読されがちだった、「天」「理」「自然」「公」という概念の歴史的な発展を追い、日本やヨーロッパと比較しつつ、中国思想の特徴を明らかにする。そこから見えてくる中国的な〈近代〉の姿。
みぞぐち・ゆうぞう=中国思想史研究者。東京大学名誉教授。
9.「建築を愛する人の十二章」
香山 壽夫 著
放送大学叢書 009
ISBN 978-4-903500-26-3

美しい都市も、美しい自然も建築と共にある。柱、窓、壁、そして大地や大空。建築の見方、作る喜びを、詩情あふれる文章で伝える。
こうやま・ひさお=建築家。東京大学名誉教授。主な作品に「彩の国さいたま芸術劇場」など。
8.「人間らしく生きる ~現代の貧困とセーフティネット~」
杉村 宏 著
放送大学叢書 008
ISBN 978-4-903500-25-6

貧困とその対策としての公的扶助を歴史的に考察し、格差社会からの出口を示す。
すぎむら・ひろし=専門は生活問題論、公的扶助論。法政大学現代福祉学部教授、北海道大学名誉教授。
7.「私たちはメディアとどう向き合ってきたか 情報歴史学の新たなこころみ」
柏倉 康夫 著
放送大学叢書 007
ISBN 978-4-903500-22-5

歴史の真の主役はメディア。新聞の誕生からグーグル問題まで。その光彩を描く6つの物語。
かしわくら・やすお=専攻はメディア論、フランス文学。放送大学名誉教授。
6.「自己を見つめる」
渡邊 二郎 著 佐藤 康邦、榊原 哲也氏 解説
放送大学叢書 006
ISBN 978-4-903500-17-1

空前の人気授業テキストが叢書化。崩れ落ちそうになる気持ちを引き締めてくれる哲学の名著。
わたなべ じろう=放送大学名誉教授、東京大学名誉教授。専攻は西洋近現代哲学。2008年逝去。
5.「比較技術でみる産業列国事情 アメリカ、中国、インド、そして日本」
森谷 正規 著
放送大学叢書 005
ISBN 978-4-903500-15-7

凋落する国、成長する国はどこか、様変わりする世界のモノつくりと日本人が生き抜く経済戦略を示す。
もりたに まさのり=専攻は現代技術論、LCA大学院大学副学長。
4.「徒然草をどう読むか」
島内 裕子 著
放送大学叢書 004
ISBN 978-4-903500-14-0

吉田兼好はなぜ「人生の達人」になったか。徒然草の後半部にその転機を読み解く、新しい徒然草の世界。
しまうち ゆうこ=国文学者、専門は『徒然草』を中心とした批評文学、放送大学教授。
3.「音楽家はいかに心を描いたか バッハ、モーツァルト、ベートーヴェン、シューベルト」
笠原 潔 著
放送大学叢書 003
ISBN 978-4-903500-12-6

「神の力」を表現したバッハ、「恋」に人間心理を読んだモーツァルト、「空虚」に降り立ったシューベルト。
かさはら きよし=音楽学者。専門は音楽学、音楽考古学、西洋音楽史。元放送大学教授。
2.「動物の生存戦略 行動から探る生き物の不思議」
長谷川 眞理子 著
放送大学叢書 002
ISBN 978-4-903500-11-9

動物の世界を行動の面からわかりやすく紹介。ありふれたスズメや毛虫がいとおしくなる。
はせがわ まりこ=生物学者。専門は生物生態学。総合研究大学院大学教授。
1.「茶の湯といけばなの歴史 日本の生活文化」
熊倉 功夫 著
放送大学叢書 001
ISBN 978-4-903500-10-2

茶の湯、いけばなを知ることは日本人の精神と生活の深部を知ること。その成り立ちを平易に解説。
くまくら いさお=林原美術館長、国立民族学博物館名誉教授、総合研究大学院大学名誉教授。
出版
左右社
ISBNとは、書籍・出版物を識別・管理するために用意された番号です。
書店等で注文する際にISBNの13桁コードを述べていただくと、よりスムーズに購入することができます。




